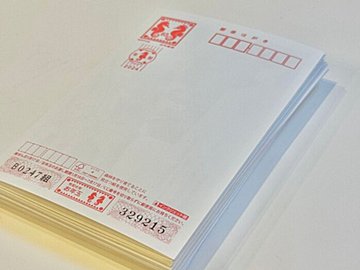料理研究家の小林まさみさん・まさるさんの家にいるのは、「盲導犬のお母さん」でした。愛犬・ヴァトンは、小林家を訪れる人にも大人気の存在。実は日本盲導犬協会出身と聞き、お話を伺ってきました。
<お話を聞いた人>
小林まさみさん
小林まさるさん
共に幅広いメディアで活躍する料理研究家で、息子の妻と義父という関係。

<教えてくれた人>: 公益財団法人日本盲導犬協会
視覚障害者の社会参加を促進するため、盲導犬の育成や視覚障害リハビリテーションなどさまざまな活動を行う。盲導犬...
ヴァトンが家に来たことで世界が広がりました
子どもの頃からの犬を飼う夢、やるなら今だと思った
実家が鮮魚店のため、子ども時代は犬が飼えなかったまさみさん。「ずっと飼いたいと思っていたけど、なかなか機会がなくて。犬を看取ることまで考えると、自分が45歳の頃までに飼い始めたいと思っていました」(まさみさん)。
その頃、盲導犬候補の子犬を預かるボランティアがあると知り、初めて犬を飼う自分にぴったりなのでは?と、日本盲導犬協会のパピーウォーカー制度に申し込んだのだそう。
日本盲導犬協会のパピーウォーカーになるためには、盲導犬訓練センター近郊に住まいがあること、車を所有していること、訓練センターでの行事に参加できることなどいくつか条件があります。小林家の場合は、申し込んでから半年くらいで雌の子犬を迎えることが決まりました。それがヴァトンです。
「子犬の名前はその子を預かるパピーウォーカーが決めるのですが、日本盲導犬協会出身の犬たちは、兄弟犬がみんな同じ頭文字の名前にするというルールがあるんです。
ヴァトンの場合は、Vが頭文字になる兄弟だったので、Vから始まる名前を男の子だった場合、女の子だった場合と3つずつ考えたのですが、最終的にバトンをつなぐという思いを込めたVatonに決まりました」(まさみさん)。
こうしてまさみさん念願の“犬との暮らし”がスタートしたわけですが、実は同居する義父のまさるさんは、最初は犬を飼うことに難色を示していたそうです。
当初まさるさんは犬を飼うことに猛反対
まさみさんと違い、まさるさんは過去に犬も猫も飼った経験があり、お世話の大変さも十分分かっていました。「ペットがいると家を空けられないし、ましてや自宅に来客が多い料理研究家の家で犬を飼うなんて。犬が嫌いな人もいるかもしれないだろって俺は反対したんだよ」(まさるさん)。
2人の攻防(!?)はヴァトンを迎える当日まで続いたそうですが、生後2カ月のヴァトンを目の前にしたらメロメロになってしまったまさるさん。「完全に孫に初めて会ったおじいちゃんの顔でした」(まさみさん)。
その日からトイレトレーニングに散歩にと小林家一丸となっての犬育てが始まったのでした。
ヴァトンの子どもたちの活躍を知るとうれしくなります
盲導犬候補だったヴァトンがなぜ今も小林家にいるかというと、小林家で過ごした後“繁殖犬”=盲導犬のお母さんになる役目を与えられ、戻ってきたから。
「繁殖犬になるとメディカルチェックや相手犬とのお見合いなどのため盲導犬訓練センターに通います。繁殖の時期はヴァトンからフェロモンが出るらしく、近所の雄犬が釣られて家の前に来たことも(笑)」(まさみさん)。
日本盲導犬協会では子犬の出産・育児は富士ハーネスという施設で行います。「毎回ドキドキでした。ヴァトンは3回出産し、6歳で繁殖犬を引退。子どもたちの中には、盲導犬として活躍する子もいます。テレビで取材された子もいて、誇らしいです」(まさみさん)。
盲導犬は知っていても、その育成を支える飼育ボランティアの存在は知らない人も多いかもしれません。そんな人にまさみさんは「犬を飼いたいときの選択肢の一つにしては」と言います。
「パピーウォーカーになると別れがつらいというのも理解できるのですが、キャリアチェンジした犬や引退犬を迎えることもできるし、何より盲導犬の育成に役立てるので、興味が湧いたら、まずは調べてみては?と思います。
私もヴァトンを迎えて世界が広がりました」(まさみさん)。「街で盲導犬を見かけると、心の中で頑張れよって思うよね」(まさるさん)。
盲導犬ってどんな犬?
目の見えない人・見えにくい人が安全に歩くお手伝いをしています
視覚障害のある人と歩行し、障害物を避けたり、段差や角で止まって教えたり、安全に歩くサポートをする。国に指定された育成団体で訓練を受け認定された犬で、「身体障害者補助犬法」によって公共施設や交通機関をはじめ飲食店やスーパーなどへの同伴が認められている。
飼育は多くのボランティアに支えられています
【繁殖犬飼育ボランティア】
盲導犬の父犬、母犬を家族の一員として迎え、交配や検査等の際は訓練センターまで連れて行くボランティア。繁殖犬引退後も面倒を見る。ちなみに出産・子育てはボランティアの家ではなく専用施設で行う。
【パピーウォーカー】
盲導犬候補の子犬を生後2カ月から1歳前後までの約10カ月間、家族の一員として迎え、人と一緒に安心して暮らすための関係づくりと家庭でのルールを教えるボランティア。
【キャリアチェンジ犬飼育ボランティア】
訓練の過程で、健康状況や性格などから盲導犬には向かないと判断された犬(キャリアチェンジ犬)を家庭に迎え、飼育するボランティア。キャリアチェンジ後にイベントなどで活躍するPR犬になる犬も。
【引退犬飼育ボランティア】
引退した盲導犬(約8年間盲導犬として活躍した後、引退した10歳前後の犬)がのんびりと余生を過ごし、天寿を全うするまで面倒を見るボランティア。
※ボランティアになるにはそれぞれ条件があります。詳しくは各盲導犬育成団体のホームページ等をご確認ください。
街で盲導犬ユーザーを見かけたら‥‥‥
盲動犬に触ったり声をかけたりせず、見守って
街で見かける盲導犬は仕事中なので、盲導犬ユーザーからの指示や周囲の様子に意識を向けています。盲動犬の気を引くようなことをすると、犬の集中力が途切れて混乱し、事故につながる恐れもあるので、見守るだけにして。
盲導犬ユーザーが困っているときは声かけを!
いきなり肩をたたいたり、体に触れたりせず、「盲導犬ユーザーさん、お困りですか」「何かお手伝いしましょうか」などと、具体的に声をかけるのがベスト。背後からではなく、正面から話しかけると伝わりやすいです。
もっと知りたい!盲導犬のこと
日本にいる盲導犬は796頭。希望する人は3000人といわれており、まだまだ足りていません※
盲導犬向きといわれるのは温厚で人との作業を楽しめる犬。いろんな場所に行き、人や動物にも会うので、攻撃性がなく順応性の高い犬が向いています。候補犬は1歳で訓練センターにて半年から1年訓練を受け、3回の評価で適性を判断。
その後、視覚障害者との共同訓練を経て正式な盲導犬に。その数は全体の3~4割程度です。盲導犬の活動期間は約8年。対して40歳で視覚障害者になった人は80歳までに最低5頭の盲導犬が必要なため、盲導犬の育成が求められています。
※24年3月末の国内盲導犬実働頭数と11年全国盲導犬施設連合会と日本盲導犬協会が行った研究調査による推計人数。
盲導犬の基本の仕事は3つ!
盲導犬ユーザーの指示に従い、安全に歩くサポートをするのが役目。できたときの盲導犬ユーザーからの声かけ「グッド!」が犬の励みに。
1 角で止まる
ユーザーが目的地までの道順を頭の中でたどる際、盲導犬が交差点などの曲がり角を知らせることが重要。角を見つけると、壁に沿ってゆっくり歩き、斜め向きで止まります。
2 段差で止まる
階段や、歩道と車道のわずかな段差などで立ち止まり、前方に段差があることを知らせます。上り段差では1段目に前足を乗せて、下り段差では段差の手前で止まります。
3 障害物をよける
そのまま歩くと障害物にぶつかりそうなときに、いったん止まるか速度を落として安全な所を通ります。道に置かれた物だけでなくすれ違う人の動きを見てよけることもできます。
盲導犬にまつわるQ&A
Q 盲導犬はほえないの?
A 痛かったりびっくりしたらほえることも。
知らない人や犬に会ったときなど、吠えたりせず落ち着いているようにパピー(子犬)の頃から教えられてはいますが、まったくほえないわけではありません。尻尾を踏まれてびっくりしたり、痛ければ、声を出すこともあります。
Q 一日中働いているの?
A ハーネスを外したらのんびり過ごしてます。
盲導犬ユーザーと一緒に歩くのは限定的な時間。家ではハーネスを外して、一般家庭にいるペットの犬と同じように過ごしています。トイレや食事、毎日のブラッシングなどのお世話は盲導犬ユーザーが行い、絆を深めています。
Q 盲導犬は長生きできない?
A 寿命は一般の大型犬と変わりません。
「盲導犬の寿命は短い」といううわさに科学的な根拠はありません。一般家庭のペットの大型犬の平均寿命と、盲導犬として活動していた犬の平均寿命を比較したところ、変わらなかったという研究データもあります。
<教えてくれた人>
公益財団法人日本盲導犬協会
視覚障害者の社会参加を促進するため、盲導犬の育成や視覚障害リハビリテーションなどさまざまな活動を行う。盲導犬の訓練センターは宮城県仙台市、神奈川県横浜市、静岡県富士宮市、島根県浜田市にある。
参照:『サンキュ!』2025年5・6月合併号「『盲導犬』を知っていますか?」より。掲載している情報は2025年3月現在のものです。監修・盲導犬写真提供/日本盲導犬協会 撮影/林ひろし イラスト/オガワナホ 構成・文/ Mikeko 編集/サンキュ!編集部