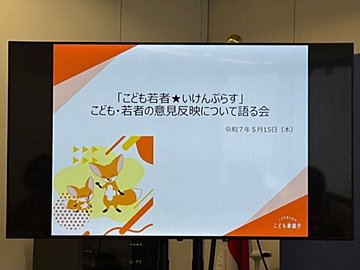2021年10月から、ニッポン放送でスタートした番組『はじめよう!フェムテック』。2022年は「フェムテック」という言葉がだいぶ浸透してきたように思います。この番組では女性特有の健康問題について、最新のテクノロジーを活かした商品やサービスだけでなく、解釈の幅を拡げて、人間が本来持つ体の機能の向上も目指しています。今回は2022年のレギュラー放送で特に反響が高かったゲストをお迎えし、スペシャル企画をお届けします。
自民党参議院議員・石田昌宏氏×内閣官房こども家庭庁設立準備室・長田浩志氏のスぺシャルトークが実現
<ゲスト>
●石田昌宏 Masahiro Ishida
自由民主党所属の参議院議員。奈良県大和郡山市生まれ、兵庫県西宮市出身。55歳。東京大学医学部保健学科卒業後、保健師・看護師として、聖路加国際病院、東京武蔵野病院に勤務。衆議院議員秘書を経て、1998年から社団法人日本看護協会政策企画室長、2002年から日本看護連盟にて常任幹事や幹事長を務める。2013年参議院選挙比例代表(全国区)にて初当選。厚生労働委員会委員長、党女性活躍推進本部事務局次長などを歴任。http://www.masahiro-ishida.com/
<ゲスト>
●長田浩志 Hiroshi Choda
厚生労働省職員。兵庫県尼崎市出身。55歳。東京大学法学部卒業後、厚生省に入省。内閣府子ども・子育て支援新制度担当参事官、厚生労働省こども家庭局総務課長などを歴任。2021年より、内閣官房こども政策推進体制検討チームに所属、2022年6月以降、こども家庭庁設立準備室・内閣審議官として、こども家庭庁の設立に関する業務を担当。
<パーソナリティー>
●東島衣里 Eri Higashijima
長崎県出身。大学卒業後、ニッポン放送に入社。現在は「中川家 ザ・ラジオショー」(金 13:00~15:30)、「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー」(土 13:00~15:00)などの番組を担当。最近、女性の健康、そして幸せについて友人と語り合うことが多くなった31歳。
人生設計を柔軟に考えることが必要な時代!
■東島アナ「今回は、このお二人のスペシャルトークが実現しました。ゲストは、看護師であり自民党参議院議員で厚生労働委員会委員長の経験もある石田昌宏さんと内閣官房こども家庭庁設立準備室・内閣審議官の長田浩志さんです。女性の社会生活にも大きく関わってくるテーマを中心に語り合っていただきました」
■石田「長田くんとは特別な接点がありまして、実は高校の同級生なんです。長田くんは長年役所でご活躍されています。子育て政策にすごく熱心で、彼の政策立案のプロセスを見ていると、自ら現場に足を運んで子どもたちや親御さんのリアルなお話を聞くというフローが入っています。ご自身も里親をされたりしていて、本当に尊敬しています」
■東島アナ「政策だけでなく私生活もライフワークのように取り組まれているのですね。長田さんが関わっていらっしゃる今注目のこども家庭庁ですが、“こどもまんなか社会”を提言されていますね。どんな組織なのか教えていただけますか」
■長田「こども家庭庁は、23年4月に設立いたします。“こどもまんなか社会”を目指す組織として、専らこども政策の事を考える省庁として設立したいと思っています。“こどもまんなか社会”には2つの想いをこめていまして、1つは文字通り『こどもを真ん中に置いて』社会全体が考えていくこと。もう1つは国の様々な重要な政策がありますが、『こどもの政策を国の政策の真ん中に置いて』いこうというもの。そんな想いを込めて、“こどもまんなか社会” の実現を図る組織として立ち上げます」
■東島アナ「背景にあるものとして、少子高齢化、結婚や出産を思いとどまるかたが増えている、というあたりも関係しているのでしょうか?」
■長田「はい、少子化は非常に深刻な状況で、こどもが減るということは長期的に考えると人口が減るということです。国の存立基盤にも関わると同時に、残念なことに、こどもの虐待、不登校、いじめなど、こども自身の育ちが非常に脅かされているという現状があります。こうした2つの側面から子どもの政策をしっかりつくっていく省庁が必要であろうと考え、こども家庭庁を設立することになりました」
■東島アナ「結婚・出産・子育てにおいて夢を感じられる社会を目指すという点においては、この番組でも扱っているフェムテックとも大変リンクします。このフェムテックを通じて、よく話題にあがるのが、出産・子育ての問題です。お越しいただいたゲストのなかで、早く出産して社会で子どもを育てる雰囲気をつくるのが大切なのでは!というご意見がありました。どのように思われますか?」
■石田「そうだと思います!そのためには、いろいろな概念をチェンジする必要があると思います。高齢化が進んで寿命が長くなっています。100歳まで生きることが珍しくない中で、今の社会のモデルは、学校を卒業して仕事について結婚をして、出産して子どもを育てながらフルで働くという当たり前の直線的な流れです。これからは40年50年、あるいは60年、80歳くらいまで働く事を考えたら、教育を受ける期間を最初にかためなくてもいいのではないでしょうか。例えば、高校を出て仕事をして子育てを始めて、落ち着いたら大学に行って、そこでまた学び直して、そんな柔軟な考え方があってもいいと思います。それぞれの生き方で、早く子どもを産んで子育てする。それを社会がどんどん認めて支えていけるようになったらいいなぁと思います」
■東島アナ「確かに、今までこの順番というものに疑問を感じずに過ごしてきましたが、どんなタイミングでも学べて働けて、という選択肢が増えるといい、という考えですね」
■石田「それにより教育も大学を卒業する人が同じ世代だけでなく、いろんな世代の人が同級生になっていきます。それはある意味多様化ですし、子育てにもいい影響を与えると思っています」
■東島アナ「こども家庭庁の目標には、地域子育ての支援というワードがありますが、石田さんが以前ご出演の際、昔の長屋のように近所の人も助け合いチームワークで子育てしていく必要性も話してくださいました。重なるところがあるなぁと思いましたがいかがでしょう」
■石田「昔の実体験をお話させていただきました。うちの第2子は自宅分娩で、近所のかたが立ち会ったり生まれた瞬間に自宅に来てくださったりした経験があるせいなのか、子どもがちょっと大きくなって歩けるようになると、隣の家でご飯を食べたり、お風呂に入ってきたりして(笑)。近所のかたも子どもが生まれた瞬間を見ていたので、自分の子どものように思ってくださって。自然に地域が子どもを育ててくれるというのは、こういうことだな~と幸せな気持ちになりました」
■長田「まさに地域子育てですね。ただ現状は、こどもを育てる喜びよりも子育ての“しんどさ”が、上回っており閉塞感があるのだと思います。これを地域全体、社会全体で子育てを支え、環境を整えていくとういうことが大事だと思っています」
経済的支援と育休制度が女性にも男性にも働きやすい環境につながる
■東島アナ「この番組では、フェムテックをテーマにいろいろなご意見をいただいてきましたが、女性が働きやすいな社会をつくるには男性の協力も必要である、というご意見も多いです」
■長田「協力にとどまっていてはダメなんだと思います。最近では男性の家事進出という言葉もありますが、女性も男性もしっかりと育児にも家事にも関わっていくことがすごく大事なのではないでしょうか」
■石田「その通りですね。協力ではなく一緒に子育てする、ということだと思います。子育ての経験は自分の成長にもつながると思います」
■長田「どちらかがこれをやって当たり前、という感覚を捨てることだと思います」
■東島アナ「このような話し合いが家庭内で当たり前にできるようになることが望ましいですね~」
■石田「胸がイタイです、笑」
■東島アナ「経済的な理由から結婚や出産を控えるというかたが若い世代を中心に多いと思うのですが、児童手当、出産育児一時金など、経済的な支援の課題はありますか?」
■長田「アンケートでも経済的なことが一番にあがってきますし、大事な課題だと思ってます。出産費用の重さというのがこれまでも問題でした。出産一時金は、岸田総理のリーダーシップにより、現在42万円ですが来年度から50万円に増額をする政治決断をしていただきました。妊婦さんや子育て家庭に対しては伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施する方針です。経済的支援は10万円を妊娠期と出産期に分けて給付をするという仕組みを今回創設しました。これらのことをこども家庭庁の取組として引き継いでいくことになります。まだまだ課題がある児童手当についてもこども家庭庁の管轄となります」
■東島アナ「こういったサポートを受けながら経済的支援と育休の制度が上手くまわるようになると、女性が働きやすい環境づくりにつながるということなんですね」
■石田「そうですね。女性が働きやすい環境づくりというのは、男性も働きやすさにつながると思います。今は女性の側面で強調していますが、無理なく働ける、時間のやりくりがしやすい、さらに仕事にやりがいを持てる、などの観点で考えていくと女性に限らず男性も働きやすい社会になっていくと思います」
■東島「育休の取りづらさというのもよく耳にしますが、ここも課題ではないでしょうか」
■石田「制度的には取り組んでいますが、まだまだ取りにくい空気はあるかもしれません。男性の育休についても進めてきたつもりですが、女性と同じように取れるわけではありませんので、ここはもっと環境を整備していかないといけません」
■長田「今、男性職員は他の休暇制度も併せて1カ月以上の育休取得をするという目標を掲げています」
■石田「最近、男性職員のかたは、育休中ということもよく耳にするのですが、実際に取得できているようで、よかったな~と思っています」
■東島「先陣を切ってやっていただけると企業にも拡がっていきますよね。男性の育休は、女性としては働きやすくなるので有り難いのですが、社会全体で考えたときに女性が働きやすい環境をつくることのメリットとはなんでしょうか?」
■石田「男性も働きやすくなることです。仕事と子育てに、生きがいを感じるためにもなります。より効果的に効率的に仕事をするための工夫をし、その中にやりがいも含まれていると思います。そういうことが表にでてくるともっといきいきした社会になると思います」
■長田「働きやすい環境で気をつけないといけないのが、女性のため、育児のため、ではなくて誰にとっても働きやすい環境をつくっていくというアプローチをしていくことです。そうしないと一部の人に優遇をして、他の人にしわ寄せがいってしまう構造になってしまいがちです」
■東島アナ「バランスを大事にしながら進めていく必要があるというお話でした。この番組のテーマである“フェムテック”という言葉は、健康問題だけではなく、男性、女性、社会全体をよくするキーワードにつながっていくと捉えています。まさにお二人のお話の通りだと思います。今後この番組に対してもアドバイスなどいただけますか」
■石田「このような番組があることで “フェムテック” が拡がっていくと思いますし、続けていただくことが社会貢献につながると思います。個人的には高校の同級生と話す機会ができてとても楽しかったです」
■長田「こども家庭庁を多くの方に知っていただきたいと思っていましたので、いい機会をつくっていただきありがとうございました」
●記事まとめ/わたしのカラダLab 編集