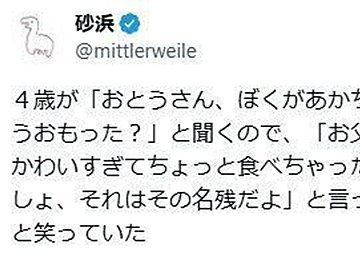園で一番の、お兄さん、お姉さんになった今は、「自分から」のやる気が最も高まるとき。お子さんの「自主性」を伸ばす絶好のチャンスです。ここでは、小学校入学までに育てたい「自主性」を伸ばすために、家庭ですぐに実践できるアイディアをご紹介します。
<監修者>汐見稔幸先生(しおみとしゆき)
●家族・保育デザイン研究所代表理事、東京大学名誉教授東京大学名誉教授。専門は教育学、教育人間学、保育学、育児学。自身も3人の子どもの育児を経験。保育者による本音の交流雑誌『エデュカーレ』編集長でもある。持続可能性をキーワードとする保育者のためのエコカレッジ「ぐうたら村」村長。NHK E-テレ「すくすく子育て」など出演。
年長さんで心がけたい「自主性」を育てるおうちのかたの関わり方とは?
5・6歳は手先が器用になったり身体能力が高まったりと、発達面でもできることが増える時期。そのため自分から、「やってみたい」「挑戦したい」という欲求が高まります。その半面、まわりからの自分の評価が気になり、失敗すると恥ずかしいという意識から、できないことはやりたがらないという傾向が出始めるのもこの時期の特徴です。
おうちのかたは、「失敗しても大丈夫」というサインを送りながら、挑戦する機会を与えてそばで見守りながらやらせてみましょう。そのときおうちのかたはできるだけ口を出さず、お子さんに考えさせることが大切。「自分でできた」という満足感が、次へのやる気につながるのです。
年長さんの「自分から」を伸ばすためにはどうしたら? お悩み別 関わり方のポイントをご紹介
「できるだけ口を出さず、お子さんに考えさせること」が大切だとわかっていても、いざ実際の生活の中でどう関わったらよいか迷いますよね。ここではよくあるお悩み別に、関わり方のポイントをご紹介します。
最初はやる気があっても、長続きしないときは、新しい刺激を与えてあげて!
やる気が高まる年長さんですが、まだまだムラがあるもの。同じことをただ繰り返すだけでは、途中で飽きやすく、続けさせるためにはおうちのかたのサポートが必要です。例えば、洗濯物をたたむお手伝いであれば、新しいたたみ方を教えたり、親子でたたむ競争をしたり。新しい刺激を与えて続けられる工夫をしてみましょう。
得意なことばかりやりたがり、苦手なことはやらないときは、やる気を誘い出す工夫を
失敗をいやがる子も出てくる頃です。大事なのは自分から「やってみよう」と思うこと。まずは、「やってみよう」という気持ちにさせるサポートをしましょう。例えば、「もうちょっとでできそうだよ」「パパも小さい頃は苦手だったけど、練習したらできるようになったよ」と声をかけるなど、お子さんのやる気を誘い出す工夫をしてみて。
アドバイスをすると、すぐにやる気をなくすときは、まずは満足感を与えてあげて
お子さんなりにプライドがあったり、「やらされている」という意識があったりすると、おうちのかたの指摘にお子さんはイライラしてしまうことも。まずは「よかった点」を伝えましょう。年長さんはほめ言葉が素直に伝わる時期。ほめられることで、意欲がぐんと高まります。満足感を得ることで、アドバイスも受け入れやすくなります。
張りきりすぎのようで心配なときは、がんばるお子さんを見守って
この時期にやる気を見せているお子さんは、しっかり成長しているという証拠です。「がんばりたい」という今のお子さんの気持ちを大事にしたいもの。疲れてきたら、いずれ自分から力を抜きます。おうちのかたは、お子さんの様子を見守り、疲れた様子が見られたら「休んでいいよ」と声をかけ、息抜きしてもいいことを伝えてあげましょう。
「自主性」を伸ばすためには安心感も大切!
例えば、「年長さんになって、甘えるようになった」「『小学生になりたくない』と口にする」「『園に行きたくない』とぐずぐずする」といった様子が見られるお子さんは、もしかすると「年長さんだからがんばらなければ」というプレッシャーや、「小学校」という未知の世界への不安を感じているのかもしれません。「自分からやるぞ」という自主性も、不安があるときには生まれにくくなってしまいます。お子さんには、「今のままでいいんだよ」という安心感を与える声をかけていきましょう。
参照:こどもちゃれんじ編集部