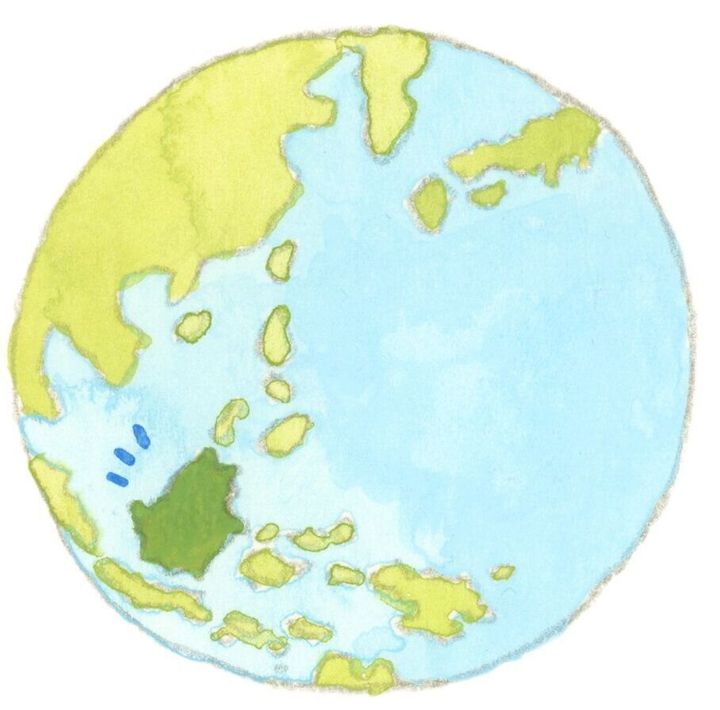取り残されているひとをなくしたい。ずっと住み続けられる地球にしたい。そんな思いと行動が「持続可能な世界」につながると『サンキュ!』は考えます。
今日よりあしたを良くするために、何かを始めたひとに会いに行く連載。
今回は日本から4600キロ離れたボルネオ島よりお届けします。
出会った人:中西宣夫さん
ボルネオ保全トラスト・ジャパン理事/サラヤ調査研究員

「ボルネオ島で、 環境問題を調べてほしい」。 在学時代に教授から頼まれ、 初めての地へ。
「ゾウを追いかける仕事、それでお給料もらえるなら楽しそうやな」。そう思って引き受けたと笑う中西さん。
大学院で国際協力や環境問題を学んでいたとき、教授からある仕事に誘われます。環境にも手肌にも優しいと人気の「ヤシノミ洗剤」のメーカー、サラヤからの依頼でした。2004年のことです。
ヤシノミ洗剤はヤシの実由来の植物油を原材料に使用しています。石油系合成洗剤に比べ環境負荷が少ないのですが、この植物油の生産のために森林破壊が進み、ゾウが犠牲になっている……そんな憶測が広がり、サラヤが実態の調査に乗り出したのでした。
世界で一番使われている植物油の 生産地で起こっていたこと
ヤシノミ洗剤の原材料の一つであるパーム油はアブラヤシというヤシから採れる油脂。
用途の多くは食用ですが、洗剤や石けん、化粧品、工業製品に至るまで幅広く活用され、世界で最も使われている植物油です。
西アフリカ原産の外来種でしたが、ボルネオ島の気候と相性が良く商業栽培に適していました。世界中で食用需要が高まっていったため、島では熱帯雨林が次々と伐採されアブラヤシ農園に変わっていったのです。
作付面積当たりの収益が大きいことも特徴で、人々が豊かになるために欠かせない作物だったと言えるかもしれません。
ここ50年の間にボルネオの熱帯雨林は40%もの面積が失われています。そこを生息域にしていた動物たちは居場所をなくしていきました。
ゾウが餌を探して農園の中に入ってしまい、罠にハマってけがをしたり、時には殺されたり。農園を荒らすゾウは農民にとっては害獣でした。
中西さんはまず、その詳細を調査し、打つ手を考えることになります。
パーム油の主な用途(農林水産省「我が国の油脂事情」より)
海外駐在の経験はありましたが、ボルネオは初上陸。「わからないことは調べればいいし、わかる人にお願いすればいい。人を探して人とつなげるのが自分の大事な仕事のひとつ」。
NGO時代のつてをたどって専門家を探し、現地の人とコミュニケーションをとりながら情報収集をしていきました。
熱帯雨林を守る活動をするにも、地元の理解なくしては進められなかったからです。英語を使わない人も多く、現地の言葉を覚えるために皆がタバコを吸いながら語らう場に入っていくことも。「禁煙してたんやけど、ボルネオに来たときだけ解禁にしてしまった」と、当時を振り返ります。
パーム油を 使わなければすむような 単純な問題ではなかった
サラヤがパーム油の使用をやめれば解決するのか?
そんな単純な問題ではありませんでした。なぜなら、パーム油は世界中で幅広い用途に使われていて、小さな企業1社が使用を止めたところで、影響はほとんどないこと。生産効率がよいため、同じ量をほかの植物でまかなおうとすれば、さらに大きな環境影響が出る可能性が高いこと。現地の経済はパーム油によるところが大きく、多くの人々の生活を支えていること……。
そこでサラヤは、パーム油の使用を続けながら熱帯雨林を守る、持続可能な方法を探っていきました。
サラヤの森と生き物を守る活動
野生動物の救出
2006年、サラヤは生物学者や環境専門家、サバ州野生生物局らとともに現地にBCT(ボルネオ保全トラスト)を設立。
BCTを通じて、傷ついたり群れから孤立した動物を保護・治療し、森に帰す活動を行っています。
命の吊り橋
アブラヤシ農園の開発によって分断された森と森をオランウータンが移動できるよう「命の吊り橋」もかけられました。
移動することで餌の獲得が容易になり、交配も進みやすくなります。
緑の回廊プロジェクト
かつて熱帯雨林だった川沿いの農園を買い戻して森として再生し、森と森をつなぐことで動植物の生息域を確保する「緑の回廊プロジェクト」を始めました。
現在「ヤシノミ洗剤」をはじめとするパーム油関連商品を購入すると、売り上げの1%がこのプロジェクトの支援に充てられます。
RSPO認証と 小規模農家支援
2004年に設立されたばかりの国際組織RSPO(持続可能なパーム油のための円卓会議)に参加。
生産地の環境と労働者の人権に配慮して作られたパーム油の普及を支援し、家庭用商品の全てに「RSPO」の認証マークを取得しています。また、RSPO認証は小規模農家が単体で取得するのは難しいため、サラヤは複数の小規模農家から買い付けを行い、グループにして認証を取るための支援をしています。
「人間は巨大なパズルの中の 小さなピースのようなもの」
ボルネオ島は「生物多様性の宝庫」といわれています。かつて豊かな熱帯雨林に覆われていたこの島では、いまだに毎年のように新種が発見されているほど。この島でしか見られない固有種も多くいます。
中西さんに「生物多様性はなぜ必要か?」という問いを投げてみました。「生態系って繊細なもので、例えば巨大なパズルのようなもの。1つが欠けたら、周りがどんどん崩れていって、取り返しのつかないものになってしまう。時間をかけても修復すべきだと思う」との答え。そして、自分を知るために多様性が必要とも。
「自分を知るためには、周りを知ることが必要。人間を知るために人間だけを見ていてもわからない。最終的には、自分を残すために自然が必要なのかもしれない……。そんなことを、ずっと考えてしまうんですよね」と笑います。

少しずつ変わっていく意識。ボルネオ島の人も 商品を手に取ってくれる人たちも
今でこそ、環境問題は多くの人の間で意識される問題となりましたが、ボルネオの環境保全活動を始めた当時、多くの人が熱心だったわけではありません。
一般の商品よりも高単価な物は「売れない」と言われました。1%の寄付をするなら、社員の給料に還元してほしいという声もありました。それでも続けることで、少しずつ理解を得られるようになってきました。
ヤシノミ洗剤を、手肌への優しさだけではなく、環境にやさしい姿勢を評価して購入してくれるお客さまが増えました。サラヤの姿勢を学びたいという企業からの問い合わせも多くあります。ボルネオ現地の農園も、現在では環境影響を意識して運営されるところが多くなりました。
地球のために、大きな志を持って働くひとがいます。
そんな人たちを、例えば何かひとつ地球にやさしい商品を選ぶなど、小さく応援することからなら、始められそう。深く神秘的なボルネオの森とそこに住む生き物たちを守ることに、誰もが無力ではいのでしょう。
協力/サラヤ株式会社 撮影/砂原文 イラスト/tent 取材・文/飯塚真希(サンキュ!編集部)
*記事は『サンキュ!』24年9月号に掲載されたものを一部加筆・修正しています。情報は24年7月現在のものです