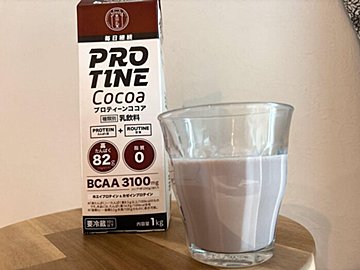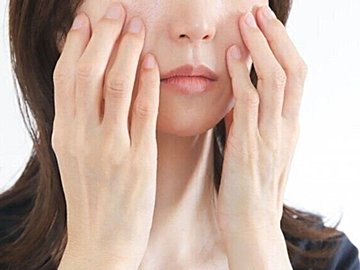3食たんぱく質を食事にちょい足しする、カーブス式を始めたら、食べても太りづらい体質になってきたという声が続出。今日からすぐにマネできる食事のポイントを専門家が解説。体調もよくなるたん活のすすめとは!?
<教えてくれた人>
藤田 聡さん
立命館大学スポーツ健康科学部教授。専門は筋肉のメカニズム解明。著書に『カーブスの健康たんぱく質ごはん』(扶桑社)。
3食"たんぱく質ちょい足し"で太りにくい体に
基礎代謝は命を維持するのに必要な最低限のエネルギーですが、加齢とともに低下し、太りやすく。運動と並行して食事にたんぱく質を"ちょい足し"すれば、筋肉が減らず基礎代謝が上昇。年齢を重ねても太りにくい体になります。
なぜたんぱく質が必要なの?
人の体は水分を除いた約40%がたんぱく質。酵素やホルモンや血液、病原体を排除する抗体もたんぱく質が主原料です。毎日十分なたんぱく質がとれないと、不調の原因にもなります。
たんぱく質は『サンキュ!』世代にメリットたくさん
●美肌、抜け毛予防、健康な爪をつくる
肌のハリにはコラーゲン、髪や爪にはケラチンというたんぱく質が影響。健康な肌、髪、爪の維持にたんぱく質が必。
●ぐっすり眠れるようになる
質のよい睡眠に必要なメラトニンの元になるのは複数のアミノ酸。たんぱく質をとるとアミノ酸が摂取できます。
●太りにくくなる
たんぱく質をとると筋肉が増え、筋肉量が多ければ自然と消費されるエネルギーも増えるので、太りにくくなります。
●骨粗しょう症予防
骨は"骨代謝"によって毎日生まれ変わります。骨代謝のためには、カルシウムだけでなくたんぱく質が不可欠。
これならできるたん活ルール1 たんぱく質は1日60~90gを目指し、毎食とる
健康な体をつくるには、3食均等にたんぱく質をとるのがポイント。たんぱく質は体にためておくことができず、また運動時に体内のたんぱく質が不足していると筋肉づくりが効果的に行われません。睡眠中は筋肉が分解され、たんぱく質が減り続けている状態なので、特に朝食でたんぱく質をしっかりとるのが重要です。
※筋トレ中の人は1日90gのたんぱく質をとるよう推奨しています(一般的に穀類や野菜からとれるたんぱく質は1日約18gなので、その分を差し引くとたんぱく質食材から72g)。1日に必要なたんぱく質の量は、体重1kg当たり1.5g×体重60kgから算出した目安です。
ちなみに1日のたんぱく質60~90gってこんな感じ
上の4つを食べれば1日のたんぱく質量をクリア。脂質やカロリーのとりすぎが気になる人は、牛乳なら低脂肪、鶏肉ならささみなど、低カロリーの食品を選ぶとよいでしょう。
【朝】たんぱく質をとって筋肉を増やすスイッチON!
朝~昼は活動が活発で筋肉が効率よくつくられるとき。朝食こそたんぱく質を多めにとりましょう。足りないときは、パウダータイプのプロテインを水や牛乳などで割って飲むのも手。
【昼】サラダに豆腐をトッピングしてたん活!
いつものサラダに豆腐をトッピングしたり、たんぱく質が豊富なさば缶をカレーの具として加えたり、"たんぱく質ちょい足し"のひと手間と工夫でたんぱく質不足を補えます。
【晩】メインでたっぷりたんぱく質をとって
鶏肉と卵の両方をメインに使うことで、たんぱく質がたっぷりとれます。良質のたんぱく質を含む卵は毎食とりたい食材ですが、コレステロール値が気になる人は1日1個を目安に。
たん活ルール2 いろんな食材からたんぱく質をとる!
ひと口にたんぱく質といっても、食品に含まれるたんぱく質は多種多様。食品ごとに"ある種のアミノ酸が多く、別のアミノ酸が少ない"ので、肉ばかり、魚ばかりに偏らず、多くの食品からたんぱく質をとるのが大事。
火を使わずに取り入れられる食材を利用して!
サラダチキン(80~100g) → たんぱく質 18g
ちくわ3本(75g) → たんぱく質 9g
納豆1パック
豆腐1/4丁 → たんぱく質 各6g
牛乳(200cc)
豆乳(200cc) → たんぱく質 各6g
卵Mサイズ1個 → たんぱく質 6g
ほかにもこんな食材でたんぱく質がとれる!
●手のひらいっぱいの肉(80~100g)…18g
●手のひらいっぱいの魚(50~80g)…12g
●小魚(10~20g)…3g
●シーフードミックス(30~50g)…3g
●ハムまたはソーセージ(1枚/ 1本)…3g
●チーズ(10~20g)…3g
●プロテイン(コップ1杯)…15g ※メーカーによります。
参照:『サンキュ!』2022年11月号「カーブス式でたっぷり食べて、スッキリ!」より。掲載している情報は2022年9月現在のものです。イラスト/澁谷玲子 構成/岡部さつき、海老澤まり子(風讃社) 取材・文/宇野津暢子 編集/サンキュ!編集部