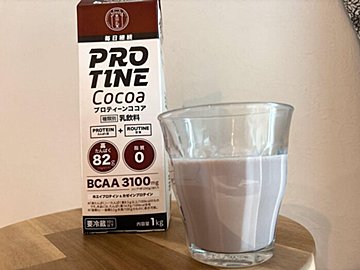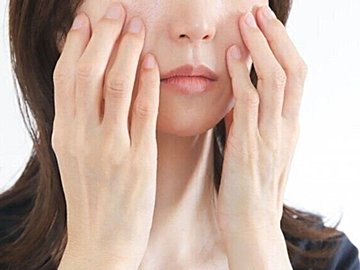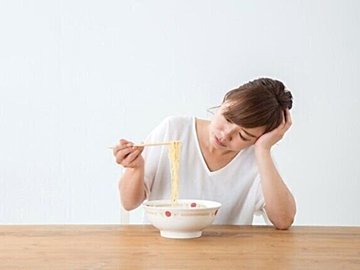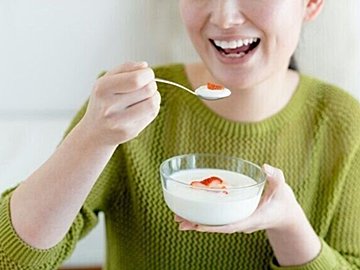健康を維持したり、病気の予防に欠かせない栄養素。そのなかでも、「たんぱく質」にはどういった働きがあるのかご存じでしょうか?
必要量がたりているからこそ、私たちは当たりまえ毎日をすごせるのですが、不足してしまうといくつものデメリットが出てくることに…。
管理栄養士と食生活アドバイザーの資格を持つライターのゆかりさんに、「たんぱく質」が不足することでどのようなことが起きるのかと、効率よくとるための食べ方について紹介してもらいます。

「たんぱく質」の働きとは?
「たんぱく質」は、炭水化物(糖質)、脂質と合わせた三大栄養素の1つです。20種類のアミノ酸が50~1,000個ほど組み合わさってつくられており、体をつくるための必須栄養素となっています。
炭水化物や脂質のようにエネルギー源として使われることもありますが、たんぱく質のおもな働きはつぎのとおり。
・内臓、筋肉、骨、歯、皮膚、髪、爪などの材料となる
・酵素やホルモンを合成して代謝や体の機能を調節する
・体内で酸素や栄養素を運ぶ
・神経伝達物質を構成する
・免疫力を高める
たんぱく質は、わたしたちの体をつくっているおよそ60兆個の細胞の主成分です。そのため、体内のあらゆる機能に関わり、健康維持にとどまらず生命維持にも欠かせない栄養素となっています。
「たんぱく質」不足になると起きることとは?
そんな「たんぱく質」が不足すると、つぎのような不調が見られやすくなります。
・筋肉量の減少、筋力の低下
・免疫力低下による感染症リスクの増大
・貧血
・集中力、やる気の低下、イライラや落ち込みやすくなる
・疲労感
・皮膚、髪の老化(弾力、張り、ツヤの低下など)
先述したように、たんぱく質は全身の細胞に関わる栄養素です。そのため、不足してしまうと筋肉、抗体、血液成分、セロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質などを十分につくれなり、さまざまな不調を招いてしまうことに……。
また、筋肉が減少することで、しわやたるみが引き起こされたり体型が崩れたりすることもあり、見た目にも悪影響を及ぼすことも指摘されているのです。
令和元年国民健康・栄養調査におけるデータを見てみると、食品からの「たんぱく質」の1日の摂取量は、どの性別・年代でも充足していることがわかっています。そのため、通常の食生活を送っていれば不足の心配はないと言えます。
ただし、偏食、欠食、ダイエットによる食事量の減少、加齢による食欲低下などが起きている場合は、たんぱく質が不足する可能性があるので注意しましょう。
「たんぱく質」を多く含む代表的な食材
ここからは、「たんぱく質」を多く含む食品についてご紹介します。
たんぱく質の摂取源には、肉類、魚介類、卵類、大豆製品、乳製品があります。水分や脂質の割合などによって100gあたりのたんぱく質量は異なりますが、ほとんどが10g以上含んでいます。
ただし、「たんぱく質」は一度に吸収できる量が決まっています。そのため、特定の食事のタイミングでまとめて食べても効果的とは言えません。そのため、何度かに分けてとる必要があるのです。
1日に必要なたんぱく質量の目安としては、1食で手のひらにのるくらいたんぱく源となる食品を組み合わせて食べることが推奨されています。(たんぱく質20g相当=豚もも肉70g+卵1個、または鮭70g+絹ごし豆腐100gなど)
なお、たんぱく質を摂り過ぎてしまうとカロリーも同時にとり過ぎて肥満の原因となったり、たんぱく質を代謝するためのビタミンやミネラルが多く消費されて不足し、それらの欠乏症が起こったり、腸内環境の悪化を引き起こす可能性も。
また、高齢者や腎機能が弱っている人にとっては、腎機能の悪化のおそれもあるため適量の範囲にとどめるようにしましょう(医師の指示がある場合は、必ずそれに従ってください)。
効率よく摂取するための食べ方や、おすすめの組み合わせ
「たんぱく質」は、大きく分けると動物性たんぱく質と植物性たんぱく質に分けられます。
動物性たんぱく質は、100gあたりに含むたんぱく質が多く、消化・吸収されやすいという特徴があります。また、肉や魚にはたんぱく質の代謝に必要なビタミンB6なども多く含まれています。しかし、種類によってはカロリーやコレステロ―ルを多く含むものもあるため、動物性たんぱく質ばかりに偏るのは避けたいところです。
それに対し、植物性たんぱく質は、おもに大豆製品のことを指します。糖や脂質の吸収を抑えたり腸内環境を整えたりといった健康効果を持つ食物繊維を含み、動物性たんぱく質と組み合わせることで、カロリーの調整に役立ちます。
このことから、たんぱく質はバランスよくどちらも取り入れていくことがおすすめです。ただし、特定の栄養素のことばかりに目を向けて、基本の食事がおろそかになっては元も子もありません。
食事の基本は、主食・主菜(たんぱく源)・副菜(野菜、海藻、きのこなど)です。1日3食と間食の中で、それぞれにたんぱく質源を取り入れるようにすると、十分な量がとりやすくなります。その中に、ご紹介した栄養豊富な食品をとり入れるようにしてみてはいかがでしょうか。