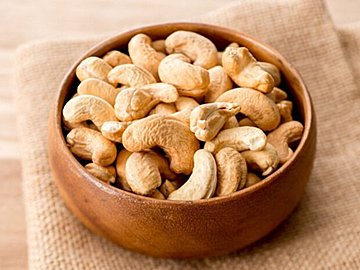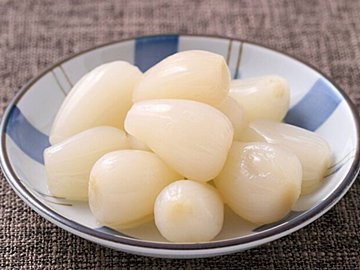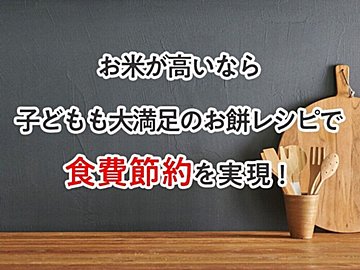ピスタチオの食べすぎはカラダによくない……とはよく聞く話ですが、なぜ悪いのか理由をご存知でしょうか?
ピスタチオに含まれる脂質には、役立つ作用を多く持つ反面、とり方を間違えてしまうと体調をくずす危険性もあるのだとか!
管理栄養士と食生活アドバイザーの資格を持つライターのゆかりさんに、ピスタチオの食べ方によって体にどのような悪影響が及ぶのかと、1日に食べてもいい量の目安について紹介してもらいます。

生活習慣病予防や栄養補給に!ピスタチオを食べる「メリット」
ピスタチオとは、中央アジアが原産とされるウルシ科の樹木に実る種子のことです。
収穫されたピスタチオは、果肉を取り除いて乾燥させ、殻を外して薄皮をむくと鮮やかな緑色の種子が出てきます。そのような見た目と、コクや甘み、特有の風味があることから、「緑の宝石」や「ナッツの女王」と呼ばれることも。
菓子材料としての使用や、そのままおつまみとして食べられることが多いですが、精製したオイルは調理用や化粧品として活用されることもあります。アメリカ、イラン、トルコで世界の9割ほどが生産されていて、日本に輸入されるピスタチオのほとんどはアメリカ産となっています。
ほかのナッツ類と同じく、ピスタチオにも脂質が豊富です。脂質は、三大栄養素の一つでエネルギー源として使われるだけでなく、つぎのような重要な働きも持っています。
・細胞膜やホルモンをつくる材料になる
・皮下脂肪として臓器を保護し、体温を保つ
・ビタミンA、D、E、Kなどの脂溶性の栄養素の吸収率を高める
ちなみに、ピスタチオの脂質中には不飽和脂肪酸の割合が高くなっていて、その中には必須脂肪酸である「α(アルファ)-リノレン酸」や「リノール酸」も多く含まれています。これらには、血栓や動脈硬化を防いだり、血圧を低下させたり、血中コレステロールのバランスを整えるなどの働きがあります。
そのほか、たんぱく質、銅、ビタミンB6、ビタミンK、ビタミンB1、食物繊維、マグネシウムなども比較的多く含まれていることから、不足しやすい栄養素の補給源として役立つでしょう。
このようにピスタチオを上手に取り入れることで、生活習慣病の予防や健康維持が期待できますよ。
肥満や体調の悪化も?ピスタチオを食べすぎる「デメリット」
多くのメリットが得られるピスタチオですが、過剰に摂取したり体質によっては思わぬデメリットが生じることもあります……。
太る原因になる
ピスタチオは、やわらかい食感とコクのある甘みがあって食べやすく、一度に多く口にしてしまうこともあるかもしれません。
しかし、ピスタチオの半分以上が脂質で占められているため、食べすぎはカロリーのとりすぎになってしまうことに……(100gあたり617kcal)。
また、ピスタチオはそのままの形だけでなく、アイスクリームに練りこんだものやペースト状のものを食べることもあります。その場合、どれだけのピスタチオが加えられているかに関わらず、シンプルな味付けのものよりも高カロリーになることが考えられます。
太るのを避けたいのであれば、ピスタチオやピスタチオを含む食品の食べすぎに気を付けましょう。
炎症が起こりやすくなる
ピスタチオに含まれている「リノール酸」には先述のようなメリットがありますが、必要以上にとりすぎるとデメリットが起こることも。
ピスタチオには抗炎症作用のある「α-リノレン酸」も含まれているのですが、「リノール酸」を過剰に摂取すると体内で炎症を起こす成分が多くつくられてしまうことが指摘されています。(100gあたり、それぞれ0.2g、16.22gの含有量)。
このことから、とくに体調不良の時やアレルギー体質の人にとっては症状が悪化する可能性があるため、食べる量に注意してください。
下痢や便秘などの不快な症状を招く
腸内環境を整え、便秘解消に役立つ食物繊維ですが、こちらもとりすぎると逆効果を生むことに……。
ピスタチオには、水に溶けやすい水溶性食物繊維よりも水に溶けにくい不溶性食物繊維のほうが多く含まれています(100gあたり、水溶性0.9g、不溶性8.3gの含有量)。
不溶性食物繊維には、便の量を増やしたり腸に刺激を与えたりする作用があります。ただし、水溶性食物繊維が不足していたり不溶性食物繊維の割合が高すぎたりすると、便の水分量が減って硬くなり便秘や腹痛などを起こすことがあるのです。
さらに、豊富に含まれる脂質が消化に負担をかけ、消化不良につながることも。こういったことから、下痢や胃もたれなどの症状が現れることもあるので、ピスタチオの食べ過ぎは避けるようにしましょう。
ピスタチオを楽しむ量とタイミングは?
上記のとおり、ピスタチオに含まれる栄養素にはメリットとデメリットの両方があります。
そこでここからは、日本人の食事摂取基準(2025年版)の数値を参考に、ピスタチオを楽しむ量とタイミングについて解説していきます。
健康な成人は1日にどれくらい食べても大丈夫?
まずは、「リノール酸」を基準として1日に十分とされる不飽和脂肪酸(n-6系)の目安量から、それに相当するピスタチオの量を算出してみました。
不飽和脂肪酸(n-6系)の1日の目安量は、30~64歳男性が11g、女性が9g。よって、それぞれおよそ68g、およそ55gのピスタチオに相当することに。
つぎに、1日の間食の目安量(1日200kcal程度)から算出してみました。すると、ピスタチオを間食として食べる場合、およそ30gでほぼ満たしてしまうことがわかったのです。
これらのことから、デメリットを抑えて楽しめるピスタチオの量は、およそ30gと言うことができます。殻をむいたピスタチオ1粒は0.6gほどとされているので、多くても1日に50粒までに収めておくことをおすすめします(粒が大きい品種の場合は、これよりも粒数を少なめに調整してください)。
ただし、ピスタチオ以外に間食をする場合は、これよりも減らすようにし、間食の目安量を超えない量にすることをお忘れなく。
どのタイミングで食べるのがいい?
ピスタチオは脂質が多くて消化に時間がかかるため、就寝前は避けるようにしましょう。消化活動が就寝中に活発になると、睡眠の質に影響を与えることが考えられるからです。
少しでも効果的に食べたい場合には、「食前30分~1時間前」のタイミングをおすすめします。
このタイミングでピスタチオを食べると、含まれているたんぱく質、脂質、食物繊維によって空腹感がやわらぎ、食事の食べすぎを抑える効果が期待できるでしょう。その際は、食物繊維が多く含まれている赤茶色の薄皮ごと食べるのが◎
さらに、少しでも満足感を高める工夫として、ピスタチオを食べる時は時間をかけ、よく噛んで風味も感じながら味わうことも意識してみてくださいね。
正しい量さえ把握できていれば、ピスタチオには多くのメリットがあります。ピスタチオのメリット・デメリットを理解し、上手にとり入れてみてはいかがでしょうか。