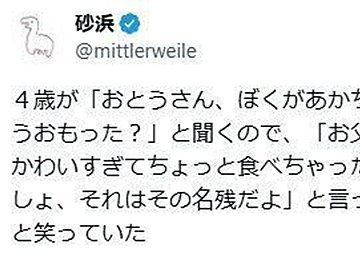「ダメ!」とばかり言ってしまったり、つい感情的に叱ってしまったり…。お子さんが動き回るようになってくると、叱り方について悩むかたが増えるようです。そこで今回の特集では、お子さんがストレスをためない、この時期のお子さんに合った叱り方を考えていきましょう。
<お話をうかがった先生>
塩崎尚美(しおざきなおみ)先生
日本女子大学人間社会学部心理学科教授。専門は、乳幼児精神保健、発達臨床心理学など。著書に『乳幼児・児童の心理臨床』(放送大学教育振興会)など。
1 愛しているよと伝えるフォローを
叱ったあとは、叱られたお子さんも、叱ったおうちのかたも、気持ちが落ち着かないものです。そんなムードを引きずらないためにも、気持ちが落ち着いたら一緒に遊んだり、ぎゅっと抱き締めたりするなどのフォローをしましょう。そうされることで、お子さんは自分が愛されていると感じて安心します。
2 ボディータッチで安心感を
大人も子どもも、体にふれられるとぬくもりを感じて、気持ちが落ち着く傾向があります。叱るときは、言葉をかけるだけではなく、手を握ったり肩に手をかけたりしましょう。お子さんに安心感を与えるだけでなく、体にふれることは行動にストップをかける効果もありますので、おうちのかたの言葉が伝わりやすくなります。
3 顔つき・身ぶりと短い言葉で
1歳過ぎ頃の子どもは、言葉はまだあまり理解できませんが、大人の表情や雰囲気などにはとても敏感です。だから今は長々とお説教するよりも、「やめようね」「いけないよ」などと短くてわかりやすい言葉とともに、顔つきや身ぶりでも気持ちを表現するのが効果的。続けることで少しずつ物事のよしあしを学習していきます。
塩崎先生からのメッセージ
【叱ることが増えるのは成長の証】
「叱るかどうか悩む」という声もよく聞かれますが、物事のよしあしを伝えるためにも、叱ることはほめることと同じように必要です。ただ叱ってばかりでは子どもはいやになってしまうと思うので、他人に迷惑をかけたときや、危険なことをしたときなど、叱る基準を決めておくのも大切です。また、別のもので気をそらすなど、叱らずにやり過ごす方法も取り入れながら、子どもの行動をあまりマイナスにとらえずに済むよう工夫しましょう。
【「ダメ」が増えるのは一時的なこと。言葉の発達とともに落ち着きます】
いたずらに悩まされるのは、実は今だけ。3歳を過ぎると言葉の理解が進むとともに、欲求をコントロールできるようにもなり、だいぶ聞き分けがよくなります。そもそも、いたずらだと思える行動も、お子さんの「何だろう?」という好奇心によるもの。他人と比べずに、叱り方の工夫や、気分転換などをしながら、おおらかな気持ちで付き合っていきましょう。
※取材時の情報です。
参照:〈こどもちゃれんじ〉