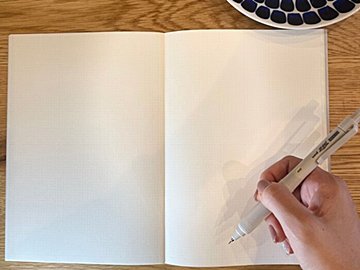「片づけたはずなのに、いつの間にかまた散らかっている…」
そんな経験はありませんか?リビング収納には、すぐに元通りに“散らかってしまう人”に共通するNGパターンがあります。
今回は、特に小さな子どもがいる家庭に多い収納の失敗と、その改善策を整理収納アドバイザーであるライター持田友里恵がご紹介します。

NG1:子どもの目線より高い場所に収納している
おもちゃや絵本など、子どもが日常的に使うアイテムを「見えない・届かない」場所に収納していませんか?
・ソファの背後や棚の上など、大人目線で置きがち
・子どもが出すときに踏み台を使ったり、手当たり次第に引っ張り出す
・結果、戻す場所もわからず、床に散らかりっぱなしに…
→対策は「子どもの目線・手の届く高さ」に収納すること。
使う本人が「見える」「届く」「戻せる」を意識すると、自然と片づけやすくなります。
たとえば、無印良品のポリプロピレンケースや、100均のカゴなどを使い、ざっくり分けてラベリングすると◎。文字が読めない子にはイラストでの表示もおすすめです。
NG2:扉つきの棚に詰め込みすぎて、開けたら雪崩状態
「とりあえず隠しておけばOK」と、見た目優先で扉の中に詰め込みすぎていませんか?
確かに閉じてしまえばスッキリ見えるのですが…。
・開けた瞬間、ものが雪崩のように落ちてくる
・出すのが面倒で、使わず放置されがち
・戻すときも適当に押し込んで、散らかりスパイラルに
→対策は「7〜8割収納」を守ること。
棚の中はぎゅうぎゅうにせず、余白を残しておくと出し入れがしやすく、リバウンドもしにくくなります。
また、棚の中に小さな仕切りボックスを入れると、種類ごとに整理しやすくなります。
NG3:“見せる収納”にしていて、中身を全部出される
インテリアとしても素敵な「見せる収納」。
でも、子どもがいる家庭では注意が必要です。
・カゴに入ったおもちゃや雑貨をすぐに全部出されてしまう
・見えるがゆえに興味を引き、片っ端から触られる
・片付けも雑然としがちで、スッキリしない見た目に…
→対策は「隠す収納と見せる収納の使い分け」
たとえば、頻繁に使うアイテムは“半透明”の収納で中身が見えるようにし、
あまり使わないものや崩されたくないアイテムは“布で目隠し”するなど、エリアによって使い分けましょう。
また、「1ジャンル1ボックス」ルールにすると子どもでもわかりやすく、戻しやすくなります。
子どもがいても散らかりにくい仕組みを!
リビングは家族みんなが使う場所だからこそ、「使う人基準」で収納を考えることが大切です。
とくに子どもが小さいうちは、目線・手の高さ・行動パターンを意識して、
“自分でできる”仕組みをつくることで、リバウンドしにくい収納が叶います。
毎回ゼロから片づけ直すのではなく、「片づけがラクになる工夫」を重ねて、心地よいリビングをキープしましょう。
■執筆/持田友里恵
整理収納アドバイザー。片づけられない主婦から片付けのプロに!“片づけ=自分を大切にすること”という信念のもと、片づけの工夫や仕組みをInstagram(@yurimochi.home)で発信中。
編集/サンキュ!編集部