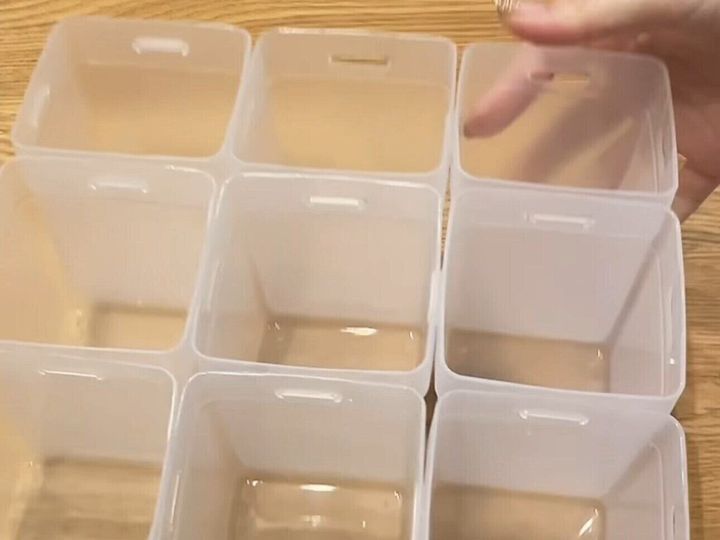「片付けなさい!」と毎日言うのは正直疲れる…。
そんな悩みを抱えるママにこそ知ってほしいのが、“自然と片付けたくなる”収納の仕組みづくりです。
子どもの発達や動作に合わせて「手が届く」「わかりやすい」「戻しやすい」収納を整えることで、驚くほどスムーズに片付けが進むようになります。
今回は、実際に効果のあった“わが家のお助け収納”を5つご紹介します!

1. 年齢に合わせた「ラベル収納」
ひらがなが読めない年齢でも、「イラストラベル」ならOK!
おもちゃ箱や収納ケースに、ブロック・人形・車などのイラストを貼るだけで、子ども自身が何をどこにしまえばよいか一目で分かります。
大きくなったら文字ラベルに切り替えるなど、成長に合わせてアレンジすることで、自立心も育まれます。
2. 手が届く高さに「1軍おもちゃ」を配置
棚の上段にお気に入りのおもちゃを置いていませんか?
子どもが自分で片付けたくなる収納には、“使うモノを取りやすく・戻しやすく”する工夫が欠かせません。
よく使うおもちゃは、子どもが立ったまま手に取れる高さに配置。
逆に、あまり使わないものは上段やクローゼット奥に移動することで、出しっぱなし防止にもつながります。
3. トレーや仕切りで「戻しやすく」
おもちゃや文房具がごちゃ混ぜになっていると、出すのは簡単でも戻すのは面倒になります。
そこで活躍するのが100均の「トレー」や「ボックス仕切り」。
カテゴリー別にスペースを分けておくと、子どもでもどこに戻せばよいかがひと目で分かります。
“定位置がある”だけで、子どもの片付け成功率はグンとアップします。
4. 出しすぎ防止に「1セットずつ収納」
遊び終わったあとの片付けが大変な理由のひとつが、“一度にたくさん出しすぎる”こと。
それを防ぐには、「遊ぶモノは1セットずつ取り出す」仕組みがおすすめです。
おままごとセット、ブロック、パズルなどを個別のボックスに分けて収納し、「ひとつ遊んだら戻す」ルールをゆるやかに取り入れるだけで、片付けのハードルが下がります。
5. 「お片付けスペース」は一緒に決める
収納場所をすべて大人が決めると、子どもにとっては「自分の場所」になりにくいことも。
「ここにする?それともこっちの方が入れやすいかな?」と、収納場所を一緒に考えることで、子ども自身が片付けに責任を持ちやすくなります。
お気に入りのシールを貼るなどして“自分だけの収納コーナー”にすれば、愛着もわき、自然と片付けたくなる流れになりますよ!
まとめ
今回は、子どもが自分で片付けたくなる!“お助け片付け術5選”をご紹介しました。
子どもが自分で片付けるようになると、ママの声かけも減ってストレスも軽減。
完璧じゃなくても、「できた!」という体験を積み重ねることで、子どもにも自信がついていきます。
まずは1つだけでも、おうちに取り入れてみてください。
片付けは“習慣化できる環境づくり”がカギになりますよ!
■執筆/持田友里恵
片付けられない主婦から片付けのプロに!“片付け=自分を大切にすること”という信念のもと、片付けの工夫や仕組みをInstagram(@yurimochi.home)で発信中。
編集/サンキュ!編集部