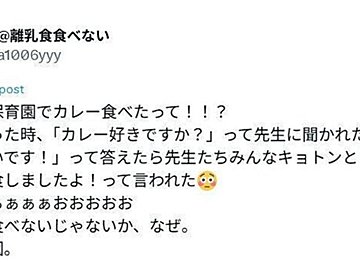行動範囲が広がり、同年代の子どもとのふれあいも少しずつ増えてくる時期。おもちゃの取り合いなど、おうちのかたが悩む場面について保育ママの浜名先生にうかがいました。
<お話をうかがった先生>
浜名紹代(はまなつぐよ)先生
育児サークルわはは代表。保育士資格をもち、保育ママとして家庭保育室を開設していた。著書に『わははで子育てキレないでボクを育てる法おしえます!』(久美出版)など。1男2女の母。
こんなときどうする?シーン別Q&A
実際に困ったときのおうちのかたの悩みに先生からアドバイスをいただきました。
シーン1 おもちゃの取り合いで自分の子を叱ってばかりに…
Q 見守りたいと思いつつも、相手の親の手前、すぐにやめさせなくてはいけないような気になって、いつも自分の子を叱ってばかりになってしまいます。 (神奈川県 なおりんご)
A 自己主張が大切な時期。親どうしで声をかけ合い少し見守ってみて。
相手のおうちのかたと「止めた方がいい?」「もう少し見守る?」など、コミュニケーションをとれるといいですね。見守るときは、ただ見ているだけではなく、「髪を引っ張ったらダメよ」「貸してって言ってごらん」など、やってはいけないことや言い方を声かけでフォローしましょう。この繰り返しで、叱られたからやめるのではなく、いけないことは自らやめられる子に育っていきます。
シーン2 乱暴されたとき、相手の子に注意すべき?
Q 月齢の高い子にたたかれたり、ボールをぶつけられたりします。その子に注意したいのですが、相手の親が無関心な場合、遠慮してしまい、なかなか注意できません。(東京都 こたこたお)
A 自分の子への対応と同じように具体的な言葉で。
相手の子に、直接注意していいと思います。でもそのときは、上手に注意したいですね。自分の子に接するのと同じように、「たたいたらダメよ。貸してほしいときは、貸してって言おうね」と具体的な言葉で伝えます。ちゃんとできたら、ほめてくださいね。
相手の親は、無関心に見えて実は子どもの乱暴な行為に悩んでいる場合も…。それを心に留めながら関われるといいですね。
シーン3 思い通りにならないとかみつく
Q おもちゃの取り合いのとき、相手の子にかみつきます。相手が泣いてもきょとんとしています。(埼玉県ゆうとも)
A かみつきそうな瞬間に本人が気づく声かけを。
かみそうになったら、まずは相手からさっと引き離しましょう。そのうえで、「かんではいけないのよ」と繰り返し伝え、かみそうになったら「こら!」と叱るのではなく、「あっ!」と大きな声で叫んで、子どもに「はっ」と気づかせる工夫を。
言われてやめるのではなく、自分で気づいてやめることが大切です。そして、かまなかったら、「今日はかまなかったね」とほめてくださいね。
シーン4 乱暴なことをされても何もできなくて大泣きしてしまう
Q 乱暴なことをされても、一切やり返せずに毎回大泣き。将来いやなことを「イヤッ!」と言えないのではと心配です。(神奈川県すーりん)
A そばにいて自己主張できるようにフォローを。
「やめてって言ってごらん」や「返してって言えるかな」など、泣かずに言えるように、具体的な言葉を伝えましょう。「…て!」などとしか言えないときは、「やめてって言ってるよ」と相手の子に伝えて、自己主張のフォローを。おうちのかたが察しがよすぎると、自分から伝える努力をしなくなってしまいます。すぐにできなくても、言わないと人には通じないことを繰り返し伝えましょう。
伝えるときはココに注意!
いざというときに感情にまかせて子どもを傷つけないように、注意点を知っておきましょう。
注意1 行動は注意するけれど、人格は否定しない
「たたく子はお母さんキライよ」はNG、「あなたは好きだけれど、たたくのはダメよ」はOK。よくない行動を注意するのはいいですが、人格まで否定する言い方はよくありません。
注意2 レッテルを貼らない
「意地悪な子」「乱暴な子」というように、「○○な子」というレッテルを貼るのはNG。自分は意地悪な子だという悪いセルフイメージをつくってしまいます。逆に、よいセルフイメージを与えると、そのように育っていきます。
注意3 頭ごなしに怒らない!
「ダメ!」「こら!」など頭ごなしに怒るだけだと、怒られたからやめるという考えになってしまうのでNG。言葉で理由を含めて教えましょう。また、どんなときも怒って手をあげるのはNG。クセになったり、エスカレートしたり、その行動を子どもがまねたりします。
浜名先生から
すぐに結果を求めずに、気長に見守りましょう。
1回言ったからといって、次からできるようになるわけではないのが1歳児。今は取ったり取られたりの経験をたくさんすることが大切で、それが上手なコミュニケーションの土台となっていきます。すぐに結果を求めずに、やってはいけないことを繰り返し教え、長い目で見ていきましょう。
※取材時の情報です。
参照:〈こどもちゃれんじ〉