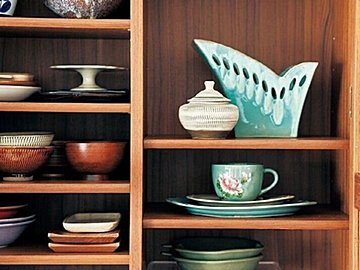小さな子どもがいるご家庭だと、部屋が片づかない状態が続いてしまうことがあります。子育てに追われるいそがしい毎日の中、いつもキレイな部屋を保つのは簡単なことではありません。でも、散らかりっぱなしの状態が長く続くと、暮らしにくくなるし、気持ちも落ち着かなくなってしまうもの。
そこで今回は、暮らしスタイリストとして、料理を始め家事全般の情報を日々発信されている河野真希さんに、小さなお子さんがいてもできる夜のお片づけ術について伺いました。

執筆/監修: 暮らしスタイリスト 河野 真希
暮らしスタイリスト・一人暮らしアドバイザー・料理家。料理や家事、インテリアなど、気持ちのいい暮らしを作る、は...
子どもが片づけできる収納を用意しよう
小さな子どもがいると、部屋が片づかないのは当たりまえ。まず大事なことは「いつでも人が呼べるような部屋にしよう」なんて意気込まないことです。でも、「四六時中ものが出しっぱなしで、落ち着かない。掃除もしにくくて、部屋が汚れるばかり」という状態が続くと、部屋だけでなく、心まで殺伐としてきてしまうもの。
完璧じゃなくていい。でも、暮らしやすい部屋を維持するためには、子どもでも片づけやすい収納をつくるのがポイントです。とはいえ、大人だって整理整頓が苦手という人も少なくないのに、ましてや小さな子どもが上手くできるはずはありません。
子どもにおすすめなのは『投げ込み収納』です。私には小学校高学年の子どもがいますが、きちんと整理整頓してものをしまえるかどうかは今でも怪しい……!でも、もっと小さいころでも、言葉が通じる年ごろになれば、とりあえず「ここに入れればいいよ」というスペースを用意しておけば、その中に放り込むことは可能ではないでしょうか。
子どもが夜寝る前に、「床やテーブルにものは出しっぱなしにしない。自分のものは全部ここに入れて」と、『投げ込み収納』できる箱やカゴなどを用意してみましょう。フタつきの箱だと、中のごちゃごちゃでも気にならないので、よりおすすめ。布をかけて、目隠しをしてもいいでしょう。何人かお子さんがいるのであれば、一人ひとつずつ用意してあげてください。
ここまでできたら、子どものお片づけはOK。あとは大人の出番です。
寝ている隙に大人が仕上げをしよう
子どもが起きているうちに片づけようとすると、「出してはしまって、出してはしまって」のいたちごっこになって、イライラの元。最後の仕上げは、子どもが寝ている隙にやりましょう。
子どもが片づけきれなかったものを『投げ込み収納』に入れたり、収納の中がいっぱいになってしまいそうなら、そっと量を減らしておいたりも◎。ただ、勝手にものを処分したことに気づかれると、かえって大事になる場合もあるので、お子さんの気持ちや性格に合わせて進めてください。
疲れのたまった夜に、片づけをするのは大変です。ただ、散らかった状態が当たりまえになると、元の状態にリセットするのがもっと大変になります。完璧にしようとは思わなくていいので、最低限床の上に出しっぱなしになっているものだけでも、その日のうちに片づけておきましょう。部屋がスッキリとした印象になり、翌朝起きた瞬間から気持ちよく過ごせます。
また、整理整頓が苦手な人は、大人にも一人ひとつの『投げ込み収納』を用意しておくと、とりあえずは、床やテーブルにものが散らばって居心地の悪い状態から脱しやすくなりますよ。
翌朝いちばんに床掃除をしよう
部屋が片づくと、掃除もしやすくなります。人が部屋にいることで舞い上がったホコリは、みんなが寝静まった夜に落ちてきます。朝起きたときに、床の上にものがない状態に片づいていれば、そのホコリを一気に取り切ることができます。
このときの掃除に使うのは、フローリングワイパーがおすすめ。掃除機を使うと、ホコリがまた舞い上がってしまうことがあるうえに、まだ寝ている家族がいたら、音で起こしてしまうかもしれません。広い部屋でも、フローリングワイパーにドライシートをつけて拭くだけなら、長くても5分以内で終わってしまうはず。いそがしい朝でも、そのくらいの時間ならつくりやすいのではないでしょうか。
夜のうちに軽く片づけておき、朝さっと掃除をするルーティンになると、ほどよくキレイな部屋を無理なく保つことができます。ちなみに、我が家では子どもといっしょに寝てしまうことが多い私が、子どもに片づけをさせ、いちばん最後に寝る夫が床のものを片づけておきます。朝は私が早く起きるので、さっと拭き掃除という流れになっています。家族ひとりが抱え込むと負担が大きくなるので、家族みんなで少しずつ役割分担できるといいかもしれませんね。
◆監修・執筆/河野 真希
暮らしスタイリスト・一人暮らしアドバイザー・料理家。料理や家事、インテリアなど、気持ちのいい暮らしを作る、はじめるためのライフスタイル提案を行う。流行や思い込みにとらわれずに、無理なく持続可能で快適な自分らしい暮らしづくりを応援。 『料理教室つづくらす食堂』主宰。