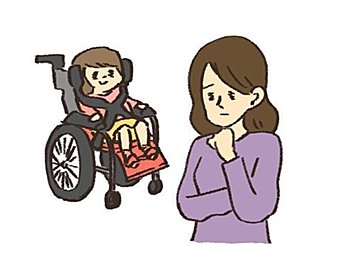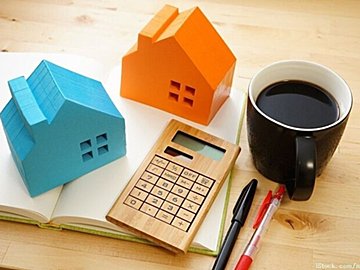障害のある二女の、将来のイメージがつかずに不安をかかえていたみのりさん。最新サービスを使ってシミュレーションしたことで、必要な貯蓄額が少しずつ見えてきました。ではこの先、どんなふうにお金を貯めて、何から優先順位をつければいいのか。LITALICOライフのファイナンシャル・プランナー、山田遼平さんが整理します。
【相談者】
みのりさん<仮名> 38歳 東京都
夫(42歳)、長女(7歳)、二女(6歳)の4人家族。フルタイムで働いています。二女には脳性麻痺があり、歩くのもおしゃべりも難しいけれど、家族で幸せに暮らす道を模索中。
【回答者】
障害のある子の教育や家庭に詳しいファイナンシャル・プランナー
山田遼平さん
金融機関、不動産・相続対策コンサルティング業界を経て、「LITALICOライフ」の講師に。障害福祉分野に精通し、生涯設計などの相談に携わっています。
親が我慢しすぎると子どもも辛くなる。自分たちの生活を守ることをまず考えて
みのり:将来、福祉のお世話になるとして、公的なサービスと民間のサービスでの、料金や質の違いも気になっています。
山田:お子さんのできることはこれから変わっていきますし、先のことはわからない中でも、今のうちから3段階のモデルケースを知っておくのがいいと思います。
たとえば、グループホームに暮らす場合、まずは全国平均を真ん中にして、生活のグレードを上げたいとすればいくらなのか、そしてセーフティーネットを使いながら切り詰めて暮らす場合はいくらなのか。
それがわかると、ご家庭の価値観と照らし合わせがしやすくなりますし、最低限を知っておけば、いざというときにも何とかなると思えます。
みのり:わかりやすいですね。
山田:その上で、何より優先して欲しいのは、親の生活を我慢しないことです。お父さん、お母さんが自分の生活を犠牲にしていると、それを見ているお子さんもつらくなります。
みのり:そういっていただけると、救われます。私も夫も、わが子に障害のあるなしにかかわらず、自分たちの暮らしも大切にしたいとは思っているんです。
でも、わが子に重度の障害があると、お母さんが仕事を辞めて介護にあたるケースがとても多くて、葛藤しながら仕事を続けています。
山田:現実問題として、学校との連携や送り迎えなどがありますので、仕事をセーブされる方は多い印象ですね。
毎年担任の替わる公立の小中学校は、先生とのコミュニケーションがポイントに
みのり:わが家は子どものためにも、お金の余裕を持ちたいと思って働いていますが、だからといって、育児や教育に力が注げなくなるのは本末転倒です。
バランス感覚を持って暮らしていきたいけれど、そういう方が周りにいないので、可能なのかどうかわからなくて。
山田:仕事を続けていらっしゃる方を見ていると、会社の理解があるかどうかが大きいようです。パートタイムだったり、フレックスや時短制度を使えたりすると、バランスが取りやすいかもしれません。
みのり:ありがたいことに、会社はとても理解をしてくれています。
小学校、中学校のことはあまり心配していないのですが、その時期に大変なことって、何があげられますか?
山田:公立の学校だと先生方の異動も多く、基本は担任が毎年変わるので、お子さんの障害に合わせた対応をしてもらうためのコミュニケーションが必要です。
親御さんがどう学校にアプローチするかは、とても重要なポイントになります。
みのり:そうなんですね。
山田:はい。感情的に要望をぶつけてしまうと、学校側と家庭とが敵対関係になるケースが多いんです。私が相談を受けたときには、客観的な事例にもとづいて「合理的配慮」を求めることをおすすめしています。
「合理的配慮」とは、障害者が社会の中で起こる困りごとを軽減するためのサポートや環境調整のことで、法律で義務づけられています。
独立行政法人がまとめている「インクルーシブ教育システム構築支援データベース」というサイトに、合理的配慮の実例がのっていますので、それを共有しながら「こういうサポートを、うちの子にもお願いできますか」と具体的な方法を話せば、先生方も協力体制がつくりやすくなります。
みのり:ただ不安をぶつけるより、サポートしてほしいことを具体的に伝えられると、先生の理解も得やすくなりそうですね。
世の中は進化している。10年後、20年後によくなっていることにもフォーカスを
山田:もう一つ、金銭的なことでいえば、お子さんのことに一生懸命になるので、ご自分たちの老後や、介護費用を見落としがちです。親族に介護が発生して、はじめてハッとする人も多いんです。
たとえば、在宅介護なら月4〜5万円、施設になると月15〜20万円がひとり当たりにかかってきます。がんばって貯蓄するのか、運用で増やすのか、保険で残すのか。
みのり:たしかに。上の子にとっても、親もたいへん、妹もたいへんでは、ダブルパンチになってしまいますよね。
私たち夫婦は資産運用にも興味がありますし、もともとはセミリタイヤしたいって話していたぐらいなんです。二女が生まれてから将来の見通しを立てられずにいましたが、二女にとっていいグループホームが見つかった土地に、夫婦で移住するのも楽しいかも。
山田:それは実現できそうですね。グループホームも最近は女性限定やヘアメイクのサービス付きなど、進化しています。10年、20年後には探す手段もさらに体系化されているでしょうし、選択肢も広がって、いい意味で迷っちゃうかもしれませんね。
子どもたちを幸せにするためには、まず、親である自分たちが幸せになること。障害の有無にかかわらず、忘れたくない大切な視点を再確認できました。とはいえ、障害のある子の育児は少数派ゆえに、苦労の多い現実があります。今回の相談を経て、みのりさんがどんな思いにいたるのか?次回に続きます。
イラスト/髙栁浩太郎 取材・文/石川理恵 企画/サンキュ!コメつぶ編集部