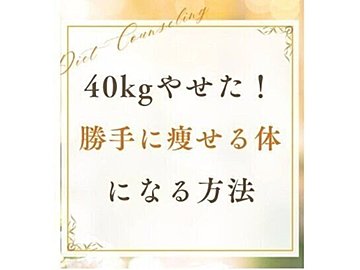外の暑さは少しずつ落ち着いてきたのに、最近疲れやすいなど体調がすっきりしないことはありませんか?実は、屋外と室内の温度差が大きい夏、日照時間が徐々に短くなる秋は自律神経の負担が増す時期。
自律神経は疲労感などの不調と関連深く、年齢を重ねるとバランスが乱れやすくなるため、日々すこやかに過ごすためにもケアすることが大切です。
ちなみに、24時間周期で体の様々な機能を調節する体内時計は自律神経の調整と関連深く、体内時計を整える暮らし方を実践すると自律神経が整いやすくなります。
今回は、体内時計を整えて自律神経をケアする4つのコツを看護師で薬膳師の薬膳ナースけいこがお伝えします。

朝日を浴びる
目が覚めたら、まずカーテンを開けて朝日を浴びましょう。朝の光は、自律神経を適度に刺激して活動モードへ切り替えてくれます。
また、光を浴びることで「セロトニン」という物質が分泌され、心が安定しやすくなります。このセロトニンは夜になると睡眠ホルモン「メラトニン」に変化し、質の高い睡眠を促すため、朝の光は夜の休息にもつながります。
昼寝や閉眼する時間を持つ
昼食後は副交感神経が優位になり、どうしても眠気が出やすい時間帯です。そこで10〜20分程度の昼寝をすると脳と体の疲れが軽減されます。可能であれば毎日同じ時間に行うことで、体内時計が整いやすくなります。
長時間寝すぎると夜の睡眠の質が低下するため短時間で済ませることがポイントです。
ただ、昼寝をする時間が取れない場合は、静かな場所で閉眼して深呼吸、リラックスすることも効果的です。耳や目など五感を休ませることは効果的な休息になります。
夕食以降の照明のコントロール
夕方以降は体が休息モードへ移行する時間帯です。明るすぎる照明やスマホ・PCなどの画面は交感神経を刺激して、休息モードへの切り替えを邪魔します。
夕食以降は照明を暖色系のやや暗めに切り替え、スマホ画面などの光を見る時間を減らす工夫が効果的です。
例えば、夕食の片づけが終わったら間接照明やスタンドライトに変える、ランプの灯かりを楽しむ。就寝前は画面を見ないなどの習慣は、体内時計、自律神経を休息モードに切り替えるのを助けるため睡眠の質を向上させます。
食事の時間を工夫する
体内時計は光だけでなく、食事のタイミングでも調整されます。特に朝食は重要で、朝食を摂ると内臓の活動が始まり、スムーズに体が活動モードに切り替わります。
一方、夕食は就寝の3時間前までに済ませることで、睡眠中の消化負担を減らし、深い眠りにつながります。遅い時間に食事を摂ると、内臓の消化活動が刺激となり寝つきが悪くなるため注意が必要です。
自律神経の不調は、単に「休めば治る」というものではなく、1日のリズム全体を整えることも大切です。体内時計と自律神経のバランスを整えて疲れにくい心身を手に入れましょう。
■執筆/薬膳ナースけいこ
大人女子が疲れにくい体と心で生きていくために東洋医学、西洋医学、脳と心の仕組みを使った暮らしに溶け込む健康習慣を発信。看護師、薬膳師として25年以上の実践経験を持ち令和元年生まれの息子を子育て中のママでもある。
Instagramは@keiko89zen
編集/サンキュ!編集部