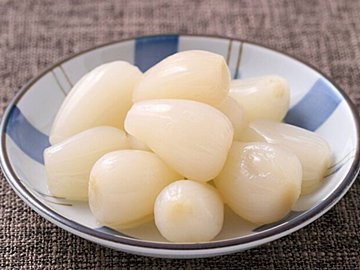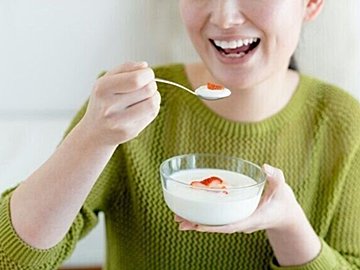誰でも出るおならですが、じつは思わぬ病気が隠れていることがあります。
少し話しにくいこのテーマについて、消化器病専門医・内視鏡専門医である天王寺やすえ消化器内科・内視鏡クリニック院長の安江千尋先生に聞きました。
- Q.おならの回数やニオイが気になる場合、考えられる病気や健康トラブルにはどのようなものがありますか
- Q.おならはどの程度から「多い・異常」と考えたらいいでしょうか
- Q.おならの頻度やニオイに影響を与える食べ物・飲み物にはどんなものがありますか。避けるべき食べ物はありますか
- Q.おならが増えたと感じたときに、自分でできるケアや生活習慣の見直しはありますか
Q.おならの回数やニオイが気になる場合、考えられる病気や健康トラブルにはどのようなものがありますか
おならは、腸内の消化・吸収の過程で発生するガスのうち、肛門から体外に排出されたものです。これは自然な生理現象で、健康な人でも1日5〜20回程度は出るとされます。
しかし、回数が急に増えたり、ニオイがきつくなったりした場合は何らかのトラブルが隠れていることがあるため、注意が必要です。
おならから考えられるおもな健康トラブルや病気は以下のとおりです。
・便秘:
便が長時間大腸に留まると、腸内細菌が食物残渣(しょくもつざんさ:食べ物のカス)を発酵・腐敗させ、硫化水素やアンモニアなどの悪臭成分を多く産生させます。これによりガスの量やニオイが増加します。
・過敏性腸症候群(IBS):
腸の運動や感覚が過敏になり、ガスが溜まりやすくなる病気です。過敏性腸症候群はストレスや食事内容で悪化し、下痢型・便秘型・混合型などがあります。
・小腸内細菌異常増殖症(SIBO):
通常、小腸はほとんど無菌状態です。しかし、何らかの理由で細菌が異常増殖すると、食物の発酵が小腸内で起こり、大量のガスが発生します。その結果、腹部膨満感や下痢、便秘といった症状が起こることがあります。
・消化不良(食物不耐症など):
乳糖不耐症やグルテン不耐症などで特定の食品を消化できないと、それらが大腸に届き発酵しやすくなります。乳糖不耐症では牛乳やヨーグルト、グルテン不耐症では小麦製品が消化不良の原因となります。
・そのほか:
炎症性腸疾患、大腸がん、膵機能低下などもまれに原因になります。症状が続く場合は受診が望まれます。
Q.おならはどの程度から「多い・異常」と考えたらいいでしょうか
医学的に明確な数値基準はありませんが、目安として以下のような状態があれば「異常」と捉えてよいでしょう。
・回数が1日20回以上と明らかに多い
・ガスがたまって苦しい、または日常生活・仕事に支障がある
・急に回数が増えた
・ニオイが急に強くなった
とくに、便秘や下痢の悪化、血便、体重減少、発熱、腹痛などを伴う場合は、消化管の病気が隠れている可能性があります。正常範囲内でも急な変化は要注意であり、変化の背景を把握することが重要です。
Q.おならの頻度やニオイに影響を与える食べ物・飲み物にはどんなものがありますか。避けるべき食べ物はありますか
食事は、おならの発生量やニオイに直結します。なかでも、以下のような食べ物や飲み物は、おならの量やニオイを強める原因となります。
・おならの量を増やす食品:
豆類、キャベツ、ブロッコリー、玉ねぎ、アスパラガスなどは、食物繊維やオリゴ糖を多く含んでおり、腸内細菌によって発酵されやすい食品です。発酵の過程でガスが発生するため、これらをとるとおならの量が増えることがあります。
また、炭酸飲料は物理的に体内にガスを取り込むため、おならの増加につながる飲み物のひとつです。
・ニオイを強くする食品:
肉や魚などの動物性たんぱく質、卵、にんにく、ニラには、硫黄化合物が多く含まれています。これらの食品が腸内で発酵するときに悪臭成分が生じやすくなります。
アルコールも腸内環境を乱し、悪臭成分の産生を促すことがあります。
・体質によって避けるべき食品:
体質によっては、特定の食品がガスの発生源になることもあります。乳糖不耐症の人は乳製品が、グルテン不耐症やセリアック病の人は小麦製品がガス増加の原因になります。
Q.おならが増えたと感じたときに、自分でできるケアや生活習慣の見直しはありますか
おならが増えたと感じたら、次のようなケアや生活習慣の見直しを行うといいでしょう。
・よく噛んで食べる:
早食いは、食べ物といっしょに空気を多く飲み込んでしまいやすく、これを呑気症(どんきしょう)と呼びます。飲み込まれた空気が腸内にたまると、ガスの量が増え、おならの原因になることがあります。
・バランスのいい食事:
肉や脂を控えめにし、野菜や発酵食品を適度にとり入れましょう。肉や脂は悪玉菌を増やし、ニオイの強いガスの原因になります。野菜や発酵食品は腸内環境を整え、おならの量やニオイを抑える効果があります。
・便秘予防:
1日あたり1.5〜2Lの水分補給を心がけ、食物繊維を適量にとりましょう(急に増やすと逆効果になる場合があります)。また、適度な運動も効果的です。
・ストレス管理:
腸の働きは自律神経と密接に関係しています。ストレスや睡眠不足が続くと、自律神経のバランスがくずれ、腸の動きや腸内細菌のバランスなどを乱します。結果としてガスがたまりやすくなり、おならが増える原因になります。十分な睡眠やリラックスできる時間を確保することも大切です。
Q.病院を受診した方がいいおならはありますか
以下に当てはまる場合は、消化器内科などへの受診が望まれます。
・血便や黒色便がある(消化管出血の可能性)
・下痢や便秘が数週間以上続く
・原因不明の体重減少
・強い腹痛や発熱を伴っている
・吐き気や嘔吐が伴う
これらは腸閉塞、炎症性腸疾患、大腸がんなど重篤な疾患のサインである可能性があり、早期の診断・治療が必要です。
取材/文:山名美穂
編集:サンキュ!編集部