「ヤングケアラー」ということばを耳にしたことがあるかた、多いと思います。
子どもをめぐる社会問題としての「ヤングケアラー」とはなにか?具体的にどんな問題があるのか?
子育て・心理分野を得意とするチャイルドコーチングアドバイザーの山名美穂さんに教えてもらいました。

大人の仕事を日常的に担う「ヤングケアラー」
「ヤングケアラー」とは、本来大人のものであるはずの仕事を、日常的に担っている18歳未満の子どものことです。
文部科学省のHPでは以下のように書かれています。
具体的な例として
・障害や病気の大人の介護を行っている
・障害や病気の大人の代わりに、家事のほとんどをしている
・仕事などでいない親の代わりに、幼い兄弟の世話全般を担っている
などが挙げられます。
ヤングケアラーに起こる問題
「ヤングケアラー」である子どもたちには、どんな問題が起こるのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。
学校に行けない・勉強する機会を失う
親の介護や兄弟姉妹の世話に費やす時間が多いと、学校に行く時間が取れなくなることがあります。
本来受けられるはずの授業や教育が受けられず、勉強が遅れていきます。
進学・就職に影響が出る
十分な学習機会が持てなければ、当然その後の進学や就職に影響が出ます。
その子どもが持っている能力を発揮することができないまま、将来の選択肢がどんどん狭くなっていくのです。
同年代と関わる機会が持てない
学校に行けないことで、同年代と関わる機会が十分に持てず、コミュニケーションの知識や対人スキルが身につきません。
学校生活をとおして得られるはずの、試行錯誤や成功の体験も積めないのです。
健康に影響が出る
家族の世話などでいそがしく十分な睡眠時間が取れないなど、健康面での悪影響もでます。
ヤングケアラーは自尊心の低い大人になる
学力が低く、家族の世話以外の体験が著しく少ない。保護者や親との情緒的なやりとりが十分にできなかった。
そんなヤングケアラーが大人になると、自分で判断ができない・対人スキルが低い・ほかの人に相談できないといった問題に直面します。
そのことによって社会生活に困難を感じ、自信を失い自尊心の低い人間になってしまいます。
次世代まで「負のスパイラル」を起こし得る
ヤングケアラーの問題は、1世代だけで終わらないこともあります。
例えば、
・学校に行けない
↓
・学力がつかない・対人スキルが低い
↓
・進学・就職に悪影響が出る
↓
・低収入な職にしかつけない
↓
・十分な収入が得られず貧困に陥る
↓
・結婚しても貧困家庭である
↓
・生活のため仕事で家を空けることが多く、子どものケアが十分にできない
・無理をして体調をくずすが知識や繋がりがなく福祉にたどり着けない
↓
・自分の子が家事を担うヤングケアラーになる
といった具合です。
ヤングケアラーは、次世代のヤングケアラーをつくり得る。これも大きな問題です。
大人になっても、誰かを世話をしたがる
ここからは、チャイルドコーチングアドバイザー、ライフコーチとしての体感的な話です。
過去にヤングケアラーだった、または類似した環境にいた人は、大人になっても誰かの世話をし続けようとする傾向があるように感じます。
そしてそれには、子どものころ「親や兄弟の役に立つことで、自分の存在意義を保っていた」ことが影響しているのではと思うのです。
自分の存在意義が内的には十分に育っておらず、他者(過去には親や兄弟)からの感謝など外的な要因に頼り続ける印象を受けます。
大人になって家族のケアから解放されても、アイデンティティを保つため「世話をする対象」を無意識に見つけようとする。
これにも上に書いたような、自尊心の低さや成功体験の少なさが影響しているといえるでしょう。
もしご自身にお心当たりがあるなら、今の自分は自由な大人であると認識し、必要であれば自治体などのサポートを受けて欲しいと思います。
ヤングケアラーは、見えにくいけど身近な問題
よその家庭のことは、外からはわかりにくいです。
しかし家族のために働き、子どもらしい生き方ができていないヤングケアラーがいるのも事実。
今は目には見えなくても、身近な社会問題として存在することを知っておいて欲しいと思います。
■執筆/山名美穂…子育て・心理分野を得意とするチャイルドコーチングアドバイザー、LABプロファイル(R)プラクティショナー。子育てを楽にするメソッドを発信している。
編集/サンキュ!編集部
※記事の内容は記事執筆当時の情報であり、現在と異なる場合があります。











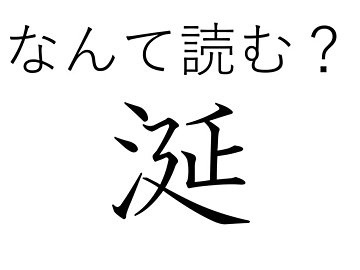



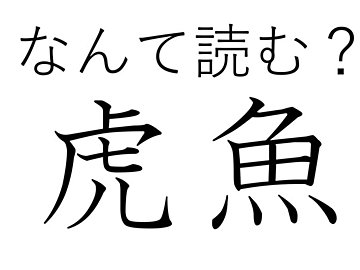





法令上の定義はありませんが、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもとされています。