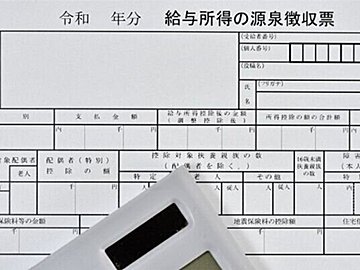会社員は会社で年末調整をしてもらっているため、確定申告は基本的には必要ないものです。でも、会社員だからこそ、確定申告をすることで得をする場合も……。今回は、会社員の確定申告について、税理士の角田圭子さんに教えてもらいました。
年末調整ってなに?
年末調整は、1年間の給与所得に対しての所得税を会社側が計算してくれるものです。毎月の給与をもらうとき、所得税が天引きされていますが、じつは、これは大まかな金額なのです。
そこで、年末に1年間の給与の合計が出るタイミングで所得税を計算し直し、調整を行います。税金を払いすぎていた場合には、税金の還付金がもらえます。会社員にとって、年末や1月ごろにもらえるこの還付金はうれしいものですね。
確定申告ってなに?
確定申告とは1月1日から12月31日までの1年間のすべての所得を計算して、確定申告書を作成し、税務署に申告・納税すること。人によっては納税だけではなく、逆に払いすぎていた税金を還付金として取り戻せる場合もあります。
会社員のほとんどは、会社で年末調整をしてくれるので自分で確定申告をする必要はありません。が、会社で年末調整をしてくれていても、さらに自分で確定申告をすることで所得税の還付金をもらえることもあるのです。
年末調整をしていても確定申告をしたほうがいいケース
会社の年末調整では控除できないものがあります。医療費控除、寄付金控除、雑損控除などです。これらは自分自身で確定申告を行う必要があり、確定申告をすることで還付金が戻ってくることもあるので、見落とさないようにしましょう。
医療費控除は年間10万円を超えたら
家族全員分の治療や診療のためにかかった医療費が年間10万円を超えた場合(所得金額が200万円以下の人は、所得金額×5%)、その超えた分を所得から控除できます。
計算の仕方は、
【医療費控除額=年間に支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額−10万円】
例えば、家族全員分の医療費が20万円かかったとします。保険で補てんされる分がない場合は、20万円から10万円を引くと10万円。この10万円が所得から控除できる金額になります。
家族のだれかが入院して医療費が多くかかった年には、医療費の計算をして、10万円を超えていたら、確定申告をすると還付金がもらえます。
セルフメディケーション税制も確認
※本マークは、一般社団法人 日本OTC医薬品情報研究会の登録商標です。
医療費控除の特例として、「セルフメディケーション税制」というものもあります。17年1月から施行されたもので、市販の薬を買った金額の合計が1万2,000円を超えたら、その超えた分を所得から控除できます(上限は8万8,000円)。
市販の薬といってもすべてではなく、特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)で、対象になる商品のパッケージにマークがあるものもあります。購入の際にもらうレシートを見ると、対象商品の横に●マークなどが印字されています。
セルフメディケーション税制の控除を受けるには、加入している健康保険の健康診断を受けていること、インフルエンザなどの予防接種を受けていることなど、健康の維持増進、疾病予防の取り組みを行っていることの条件があります。
医療費控除と同時に利用することはできないので、医療費控除かセルフメディケーション税制か、どちらのほうが還付金の戻りが多くなるかを計算して確定申告するといいですね。
寄付をしたら控除を受けられる
国や地方公共団体などに寄付をした場合にも所得控除を受けることができます。
1年間の寄付金から2,000円を引いた額が、所得税の寄付金控除額となります。所得税だけでなく、住民税からも控除される場合があります(年収、家族構成により控除上限額が決まっています)。
なお、「ふるさと納税」は納税先の自治体が5カ所までなら、確定申告の必要がない「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できます。これは、確定申告をする必要のない給与所得者が適用を受けられるもので、寄付した自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出します。
1年間で6自治体以上に寄付をした場合は、自分で確定申告をすることになります。
自然災害などを受けたときは雑損控除
地震・火事・台風などの自然現象、生物・人の行為が原因となる災害や盗難、横領などによって資産が損なわれた場合に適用される控除です。恐喝や脅迫、オレオレ詐欺などは控除の対象には入りません。
住宅ローン控除の1年目は確定申告
マイホームを購入して住宅ローンを組んだ場合、住宅ローン控除は初年度に限り年末調整で申告できません。自分で確定申告をしてください。2回目以降は、会社の年末調整で控除を受けられます。
確定申告をしなければならないケースも
確定申告をしたほうがいいケースは、確定申告をしてもしなくてもいいもののことです。確定申告をするかどうかは自分で決められます。
ここでは、会社員でも確定申告をしなければならないケースを紹介します。
●年収2,000万円を超える場合
会社に勤めていても、年収が2,000万円を超える人は年末調整をしてもらえません。これは、所得税法の規定によるもの。会社から年末にもらう源泉徴収票や生命保険控除などといっしょに、自分で確定申告をします。
●副業で所得20万円を超える場合
会社とは別に副業などを持っているかたで、その所得が20万円超になると確定申告をする必要があります。会社からもらった年末調整済みの源泉徴収票といっしょに、自分で副業の所得を計算して確定申告します。
年末調整に出し忘れたものがあったら確定申告を行おう
会社の年末調整で控除できる書類を出しそびれたり、伝え忘れたことがある場合も、確定申告をすることで還付を受けられます。
・生命保険や地震保険などの控除証明書
・扶養家族が増えたこと
・結婚したこと(配偶者控除・配偶者特別控除を受けられる範囲内の場合)
こちらの場合も、会社からもらった年末調整済みの源泉徴収票や関係書類といっしょに、控除から漏れているものを記入し、確定申告します。
「あの年、確定申告をすれば税金が戻ってきたのに」と心当たりのあるかた、確定申告は過去5年にさかのぼって申告ができます。