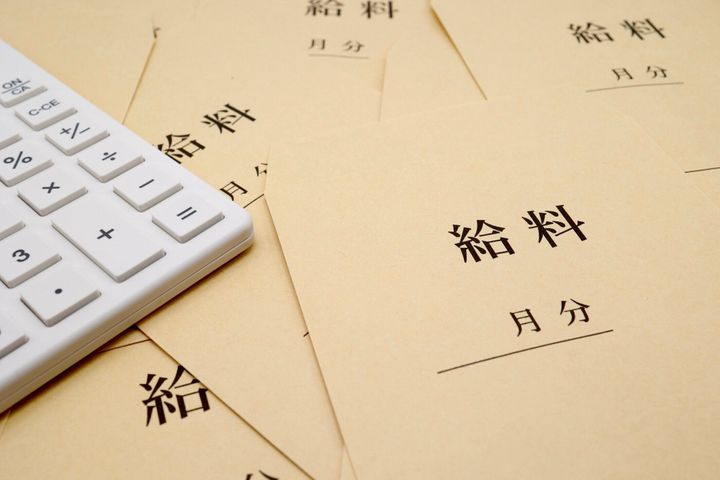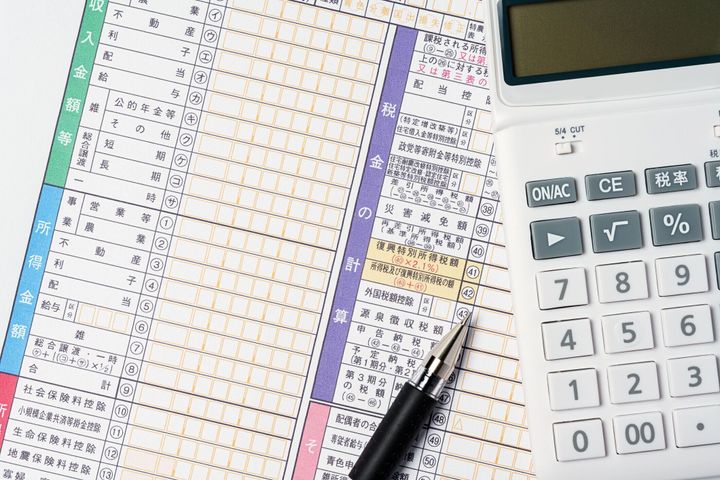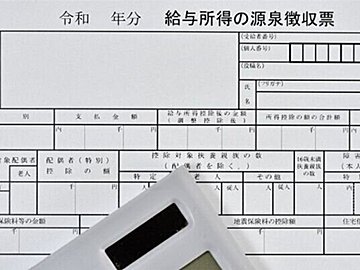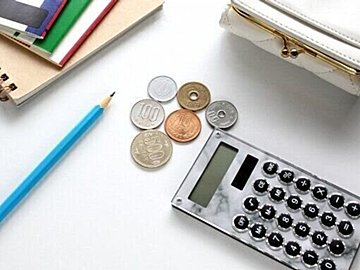節税は納税者の権利!申告すれば手取りが増えます!そこで会社員・パートの節税についてご紹介。企業に勤めていて、税金を払っている会社員やパート(条件あり)の人は、勤務先で節税の手続きをしてもらえます。

<教えてくれた人>: 元国税専門官 金融ライター 小林義崇
04年より東京国税局の国税専門官として、相続税の調査や所得税の確定申告業務に従事。17年にフリーライターに転...
「年末調整」によって節税につながる控除を受けられる
会社員やパートの給与から天引きされている所得税額は、仮に計算されたもの(源泉徴収)。年の途中で、扶養家族が増えたり、家を購入したりすると、所得税の金額が変わります。「実際の所得税」と「仮の所得税」の差額を精算するために会社側が行うのが「年末調整」です。毎年10~11月ごろに渡される書面に記載し、提出することで、会社が手続きをしてくれるので、比較的手間がかかりません。節税効果を得るために大事なのは、漏れなく記入し、必要書類を提出すること。正しく提出しないと、所得税の負担が増える場合もあります。
●「年末調整」で手続きできる控除
【配偶者控除、配偶者特別控除】収入が一定以下の配偶者がいる
【扶養者控除】収入が一定以下の扶養親族がいる
【社会保険料控除】社会保険料を支払った
【生命保険料控除】生命保険料を支払った
【地震保険料控除】地震保険料を支払った
【住宅借入金特別控除】住宅ローンを組んでいる(2年目以降)
【障害者控除】本人や配偶者、扶養親族に障害がある
【寡婦控除、ひとり親控除】配偶者と離婚や死別、またはひとり親である
【小規模企業共済等掛金控除】iDeCo(確定拠出年金)などに加入している
●配偶者の収入の記入金額に誤りがあると、差し戻される場合も!
例えば、配偶者が掛け持ちで仕事をしているのに、1社分の収入しか申請していないと、税務署から正しく申告するよう指導される場合が。節税効果にも影響があるので要注意!
「年末調整」で手続きできない控除は、確定申告が必要
給料の収入が1社のみの人で、年末調整後に扶養家族が増えた場合や、年末調整の期限までに保険会社の保険料控除証明書が間に合わなかった場合、年の途中で退職した場合などは、確定申告を行えば控除を受けられます。また、そもそも年末調整では手続きできない控除も。下記の一覧表の要件に当てはまる場合は、会社の「年末調整」とは別に確定申告で手続きをする必要があります。
●「年末調整」で手続きできない控除
【医療費控除】医療費が年10万円(総所得額等が200万円未満の場合は、総所得額等の5%)を超えた
【寄付金控除】ふるさと納税※や寄付をした
【住宅借入金等特別控除】住宅ローンを組んだ(1年目のみ確定申告が必要)
【配当控除】株式などの配当金を受け取った
【雑損控除】災害や犯罪などで被害を受けた
※「ワンストップ特例制度」で申し込んだ場合は、確定申告は不要。
●会社が負担してくれない仕事の経費は「特別支出控除」で取り戻す!
仕事内容や勤務先の条件によっては、仕事に関連する経費の自己負担が多いというケースも。下記のような費用の1年分の合計額が「本来の給与所得控除×1/2」を超えたら、「特別支出控除」として確定申告をしましょう。
例えば……
・通勤費用 ・仕事のための旅行費用
・転勤に伴う転居費用
・職務のための研修費用
・職務に関わる資格取得費用 ……など
●こんなケースも確定申告が必要!
□ 年の途中で退職し、年末調整ができなかった
□ 年末調整で申請し忘れていた控除がある
□ メインの給料以外の収入が20万円超ある
年収いくらから税金がかかるの?
●年収100万円超で住民税、年収103万円超で所得税がかかります
今何かと話題になっている「年収の壁」ですが、現時点(24年12月)での税制では、年収100万円超で住民税がかかり、年収103万円超で所得税がかかります。夫が会社の配偶者控除を受ける場合は妻の年収103万円まで、妻の年収106万円以上で配偶者特別控除となり、年収150万円超で配偶者特別控除の額は段階的に減っていき、年収201万円超で控除の対象外になります。
●手取りが減る要注意ゾーン
住民税・所得税が引かれても、手取りが減る影響は小さ目。年収106万円以上※2、年収130万~年収150万円までのゾーンは社会保険制度上、配偶者の扶養から外れるので、社会保険料の支払いにより手取り額に影響が!パート先の社会保険に加入し会社と折半で保険料を支払うか、入れない場合は、自分で国民年金などの社会保険に加入し、保険料は全額自己負担に。
<教えてくれた人>
元国税専門官 金融ライター 小林義崇さん
04年より東京国税局の国税専門官として、相続税の調査や所得税の確定申告業務に従事。17年にフリーライターに転身。著書に『図解でわかる 絶対トクする!節税の全ワザ』(きずな出版)など。
※1 配偶者の年収によって控除額は異なる。夫の年収が1195万円以上の場合は控除の対象外。
※2 従業員数51人以上の企業、雇用期間が2カ月超、労働時間週20時間以上、賃金が月8万8000円以上などの基準を全て満たす場合。
※この特集で掲載している情報は、24年12月23日現在のものです。
参照:『サンキュ!』2025年3月号「かしこく節税して手取りを増やす本」より。掲載している情報は2025年1月現在のものです。構成・文/宮原元美 編集/サンキュ!編集部