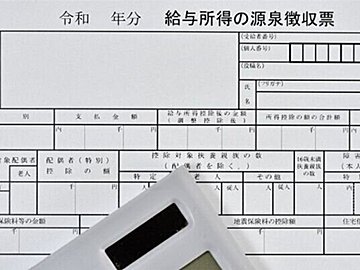妊娠から出産までには、たくさんの医療費がかかります。「出産育児一時金」など、国からの助成もありますが、出産費用が予想以上に大きくかさんでしまった場合は、その年分の「医療費控除」で税金が返ってくる可能性があります。
「医療費控除」の仕組みと、妊娠・出産にまつわるお金について、税理士の角田圭子さんに詳しく教えていただきました。
出産にかかったお金は「医療費控除」で還付金がもらえる!?
「医療費控除」とは?
1年間(1月から12月まで)に支払った医療費が合計10万円超となった場合、翌年に確定申告をすることで、払いすぎた所得税が一部戻ってくるのが「医療費控除」という制度です。
対象となるのは、主に病気やけがなどの治療・療養にかかった医療費。美容目的の治療費は控除の対象に入りません。
また、病院や薬局などで支払った費用だけではなく、通院のためにバスや電車を利用した場合は、その交通費も対象として認められます。
家族全員分の医療費を合算することができ、最も収入が多い人が申告をするのが一般的です。
17年1月には医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」がスタート。健康管理のために健康診断や予防接種などを受けている人が、薬局・ドラッグストアで販売されているOTC医薬品を年間1万2,000円超購入した場合に、所得控除が受けられるというものです。
従来どおり10万円超の医療費を申告して「医療費控除」を受けるか、この「セルフメディケーション税制」を利用するかは、申告する本人が選択できます。
出産費用は対象になる
平均50万円といわれる出産費用ですが、国から「出産育児一時金」として42万円がもらえるので、実際に自分で支払う分はそれほど大きな金額ではありません。もちろん、なかには出産費用が42万円を下回る人もいます。
もし42万円を超える費用がかかった場合は、「医療費控除」の対象としてほかの医療費に合算することができます。病院でもらう領収書、医療費通知は控除の手続きに必要になるので、なくさないようにしっかり保管しておきましょう。
領収書、医療費通知をもとに「医療費控除の明細書」を作成し、所得税の確定申告に添付して提出します(医療費通知は提出し、領収書は自宅で5年間保管します)。
「医療費控除」の対象になる妊娠・出産のお金
妊娠・出産は病気とは見なされないため、健康保険が利用できず、基本的に全額自己負担となります。自治体の助成制度などで費用の一部は負担してもらえますが、それでも自分で支払った分を合計すると10万円を超えるケースは決して少なくありません。
妊娠・出産関連の費用で「医療費控除」の対象になるものは下記のとおり。しっかりチェックしておきましょう。
・ 妊娠中の定期健診費用
・ 分娩・入院費用
・ 通院のための公共交通機関の運賃
・ 出産時に緊急で利用するタクシー代
・ 入院中の食事代 など
なお、次の費用は医療費として認められないため、控除の対象にはなりません。
・ 妊婦用下着・衣類など
・ 出産準備品の費用
・ 里帰り出産のための帰省費用
・ 自己都合による入院時の差額ベッド代
・ 医師や看護師への謝礼 など
いくら戻ってくるの?
「医療費控除」は10万円を超える医療費を申告するものですが、実際にはいくら戻ってくるのでしょう。
ここで気をつけたいのが、10万円を超えた分がそのまま戻ってくるわけではないということ。そもそも「医療費控除」は所得税を軽減する仕組みなので、申告する人の所得額によっても大きく異なります。
① まずは、「医療費控除額」を計算します。
--------------------------------------------------------------------
医療費控除額=[1年間に支払った医療費の合計]ー[補てんされる金額(※1)]ー[10万円(※2)]
--------------------------------------------------------------------
※1 健康保険から支給される「高額療養費の給付」や「出産育児一時金」、生命保険から支払われる「医療保険の給付金」など。
※2 総所得金額200万円未満なら総所得金額の5%。
② 次に、「還付金額」を計算します。
--------------------------------------------------------------------
還付金額=[医療費控除額]×[所得税率(※3)]
--------------------------------------------------------------------
※3 所得税率とは、課税される所得金額に応じて決められている税率(5〜45%)のこと。
この還付金額が実際に戻ってくる金額を指します。
こんなケースではいくら戻ってくる?
Aさんの場合は「医療費控除」でいくら戻ってくるのか、計算式に当てはめてみましょう。
<Aさんの条件>
・ 出産費用・・・・・・60万円
・ 出産育児一時金(補てんされる金額)・・・・・・42万円
・ 所得税率・・・・・・10%
① 医療費控除額は、
[1年間に支払った医療費60万円]ー[出産育児一時金42万円]ー[10万円]=医療費控除額8万円
② 還付金額は、
[医療費控除額8万円]×[所得税率10%]=還付金額8,000円
つまり、Aさんの「医療費控除」での還付金は8,000円。さらに、翌年分の住民税(一律10%)も8,000円軽減されます。
「医療費控除」はどのように手続きするの?
「医療費控除」の手続きには、確定申告が必要です。
ある年の1月1日から12月31日までの医療費に関しては、翌年の確定申告時期(2月16日から3月15日)に手続きを行いましょう。ただし、還付申告(所得税が戻る申告)だけなら、翌年1月1日から手続きを行うこともできます。
手続きに必要な書類は下記のとおりです。
【「医療費控除」の確定申告に必要な書類】
□ 確定申告書
□ 医療費の領収書
□ 源泉徴収票
□ マイナンバー(または通知カードと身分証明書)
□ 印鑑
□ 通帳またはキャッシュカード(振込口座が確認できるもの)
書類が準備できたら必要事項を記入し、直接税務署に持参するか、郵送で提出することができます。また、インターネット上で手続きをすませる方法も。
期日間際になると税務署は混み合いますので、余裕を持って手続きできるように、早めに準備しておきましょう。