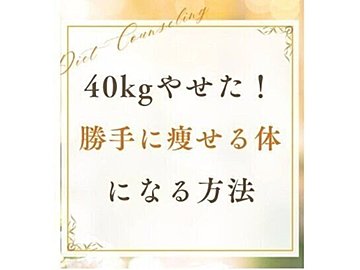体が冷えると自律神経のバランスが崩れます!「体質だから変わらない」と、体の冷えを放置しているのは危険!実は、冷えと自律神経の乱れは密接に関係。温活で冷えを解消すれば、さまざまな不調も改善できます。

監修: 医師・イシハラクリニック副医院長 石原新菜
イシハラクリニック副院長。主に漢方医学、自然療法、食事療法により、種々の病気の治療にあたる。2児の母でもある...
体が冷えると自律神経のバランスが崩れます!
自律神経の働きの1つに、体温調節があります。暑いときは汗を出すことで体温を下げる、寒いときは体を震わせたり、脈を速くすることで体温を上げるといったように、無意識に体温を一定に保とうとするのです。そのため、体の冷えを放置していると、交感神経が頑張って体温を上げようと、過剰に働くことに。結果、バランスが乱れてしまいます。特に女性は筋肉量が少ないため、体が冷えやすいので意識的に温める=温活が重要。温活すれば誰でも冷えは解消できます!
体の冷えと自律神経の関係
【体が冷える】外気温が低くて体が冷えると、これ以上体温が下がらないように、体に熱を作る仕組みが発動。
【温めようと交感神経がムダに頑張る】その結果、交感神経がグンと優位になり、脈拍が上昇。体の震えや鳥肌などの反応が現れる。
【自律神経が乱れる】体が温まらないと、交感神経ばかりが優位な状態が続いてしまい、バランスが取れなくなる。
体の冷えは次の順番で深刻になっていきます
ひと言で「冷え」といっても、深刻度はさまざま。まずは自分の状態を確認!
PHASE 1【末 端】手や足先が冷たい
PHASE 2【下半身】足がむくみやすい
PHASE 3【おなか】おなかを触ると冷たい
PHASE 4【全 身】手足も内臓も冷え冷え
自律神経がいつも整っている人になれる!“温活”の5大ポイント
冷えの原因は日常生活の中にあります。下記の5つのポイントを意識するだけで、冷えない体に!
1 朝食は抜かない
朝食を抜くとエネルギーが不足してしまい、体温が上がりにくくなります。ヨーグルトでもいいので、なにかしらおなかに入れることが大切。できることならみそ汁など、温かい物を取ると冷え解消に効果的。
2 しっかり眠る
睡眠不足やストレスは、冷えを悪化させる原因になります。そして、体の冷えは睡眠の質を低下させるため、悪循環に陥る可能性が……。寝る前にしっかり体を温め、よく眠ることで悪循環を断ち切りましょう。
3 飲み物は常温以上
冷たい物ばかり飲んでいると、体の内側から冷やされて、体温が下がってしまいます。温かい飲み物がベストですが、せめて常温以上を心掛けて。コーヒーなどに含まれるカフェインは体を冷やすため、温活には白湯(さゆ)がおすすめ。
4 湯船につかる
時間がないからとシャワーだけで済ませる人も多いですが、冷えが気になる人はぜひ湯船につかる習慣づけを。ぬるめのお湯にじっくりとつかることで、全身がしっかりと温まります。副交感神経が優位になり、リラックス効果も。
5 軽い運動をする
運動によって筋肉量を増やすことで、自分の体の中で熱を作れるようになり、冷えにくくなります。わざわざジムに通わなくても、歯磨きしているときに軽くスクワットをするだけでもOK。小まめに体を動かして。
石原新菜さんのイチオシちょい足し白湯レシピ
白湯には体の内側から一時的に温める効果がありますが、飲んでしばらくするとその効果はなくなります。そこで、温め効果を持続させる成分を含む食材をちょい足し!
●しょうが
しょうがの辛み成分であるショウガオールが体を温める。
●シナモン
体温を上げ、脂肪燃焼を促進する効果が漢方でも重宝される。
●大葉
ピリッとした辛み成分が体を温めたり、血行を改善する効果が。
冷えを感じたら……その場で深呼吸しよう
●自律神経の働きで唯一自分がコントロールできるのは呼吸
基本的に自律神経は自分の意思でコントロールすることはできませんが、呼吸だけは例外。体が冷えたら、深く息を吐いて深呼吸することで副交感神経を優位にし、バランスを保てます。
<教えてくれた人>
医師 石原新菜さん
イシハラクリニック副院長。主に漢方医学、自然療法、食事療法により、種々の病気の治療にあたる。2児の母でもある。最新著書は『免疫力アップ!温活ランニング』(主婦の友社)。
本書は『サンキュ!』20年1月号~25年2月号に掲載された記事を抜粋、加筆、再編集したものに新規の記事を加えています。
サンキュ!アンバサダー、『サンキュ!』読者の情報は掲載当時のものです。
不調が続いたり、健康に不安がある場合は、かかりつけ医や医療機関にも相談しましょう。
参照:『サンキュ!』2025年4月号「自律神経セルフケアBOOK」より。掲載している情報は2025年2月現在のものです。構成・文/杉澤美幸、サンキュ!編集部 編集/サンキュ!編集部