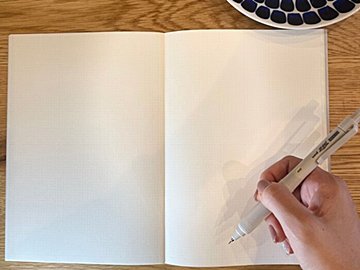「片付けたはずなのに、なぜか疲れる」「時間がかかって毎回イライラ…」
その原因は“収納方法の非効率さ”にあるかもしれません。
スッキリ見える収納でも、行動の手間が多ければストレスが蓄積されるもの。
本記事では、日々の片付けがスムーズになるよう、効率の悪い収納と改善方法を整理収納アドバイザーであるライター持田友里恵がご紹介します。

NG1:1つのモノを戻すのに何ステップもかかる
収納ボックスにフタがあって、さらにそのボックスが棚の奥に…
そんな「面倒な動作」が積み重なると、戻すのが億劫になり、出しっぱなしの原因に。
改善ポイント
・アクション数は「最大2ステップ以内」に
・フタ付きボックスより“引き出し式”や“オープン収納”が便利
・手前に使うモノ、奥にストックといった配置の工夫も◎
「開ける→しまう」だけで完了する仕組みを目指しましょう。
NG2:カテゴリをまとめすぎて探し物が増える
「文房具」や「日用品」など、大カテゴリでザックリ収納していませんか?
モノが多いと、その中から目的のものを探すだけで時間がかかり、出す→戻すの流れが面倒に。
改善ポイント
・“よく使うモノ”は細かく分類し、個別ポーチやケースで仕切る
・よく似たモノ(ペン・ハサミ・カッターなど)は使用頻度別に分ける
・透明ケースやラベル付きで「見てすぐわかる」工夫を
まとめすぎず、細分化しすぎず。使う人が “迷わない”ラインを探すのがコツです。
NG3:必要な道具が家のあちこちに分散している
ハサミはリビング、テープは玄関、ペンは寝室…と用途がバラバラに点在していませんか?
“使いたいときに見つからない”ストレスが、片付けの効率を下げてしまいます。
改善ポイント
・「使う場所ごと」にセット収納を
例)玄関に“宅配対応セット”(ハンコ・ボールペン・カッターなど)
・“家の中のよく使う道具”は、1か所に集中管理もあり
・使用頻度の高い道具は“見える収納”にしてもOK
分散収納は管理も探すのも大変。まとめておくと補充もしやすくなります。
収納の“使いやすさ”が時間を生みます。
収納は「見た目の美しさ」だけでなく「行動のしやすさ」も大切!
何気ない1つ1つの手間が、トータルで “片付けのしんどさ”になっていきます。
・戻すのに時間がかかる
・モノを探すのに時間がかかる
・使いたいものが見つからない
このような状態が続いている場合は、一度 “行動導線”を意識して収納の見直しをしてみてください。
少しの工夫で、毎日の片付けがぐっとラクになりますよ。
■執筆/持田友里恵
整理収納アドバイザー。片付けられない主婦から片付けのプロに!“片付け=自分を大切にすること”という信念のもと、片付けの工夫や仕組みをInstagram(@yurimochi.home)で発信中。
編集/サンキュ!編集部