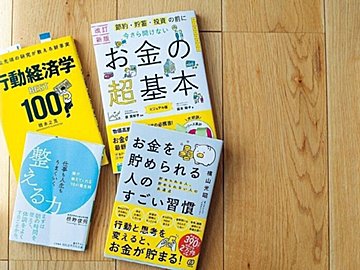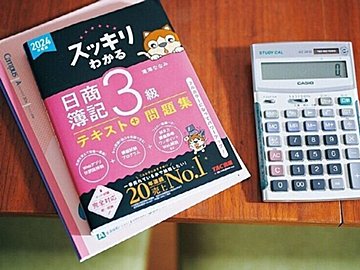マネーリテラシー(略してマネリテ)とは、お金についての知識や判断力。国の方針で2020年に小学校、21年には中学校、22年には高校で金融についての教育が義務に!日本でいちばん売れている※月刊マネー誌の編集長にマネリテについて聞いてきました。

<教えてくれた人>: 『ダイヤモンド・ザイ』編集長 熊谷久美子
創刊時より『ダイヤモンドZAi』に携わり、2024年より編集長に就任。『月刊マネー誌ザイが作った新NISA入...
“老後のお金は自分でつくってね”
『サンキュ!』編集部/(以下【サ】)「マネーリテラシー」とは?ザクッと一言で教えてください!
「限られたお金をどう使うか?を“自分で考える力”のことですね」
【サ】じゃ、国が国民のマネリテを上げようと頑張っているのはなぜ?
「昔のように国や会社が老後をまるっと面倒見てくれる時代ではなくなったからではないでしょうか。年金がなくなることはないですが受給額は年々減り、退職金も減ってます。そこで国はiDeCoやNISAなどの制度を充実させて『自分でも資産を増やす工夫をして老後に備えてね』と後押ししているんです」
【サ】わぉ(汗)。お金のことを人まかせにしていられない時代が来て、マネリテがより大切になってきたのですね……。
知らないとソンする、知っていればトクする
「今はお金を払うにしても現金やカード、電子マネーにQRコード決済など方法はいろいろ。資産の増やし方も貯蓄に加えて投資が一般的になってきて多彩に。お金にまつわる選択肢と情報があふれる現代は、それらをうまく使えばトクするチャンスが増えて、より豊かに暮らせます。
そのときマネリテが大いに役立ちます。億単位の資産を築いた投資家も、最初はそうしておトクなお金情報を駆使して支出を減らし、投資に回すお金をつくることから始めた方が多いんですよ」
【サ】それはちょっとワクワクしますね~。
「逆にマネリテが低いと情報に振り回されてしまう。今はSNSで個人が気軽に情報発信でき、真偽が不確かなお金情報が飛び交っています。『これは正しい情報?』と立ち止まって考える力がないと、うっかりソンすることも。
自分に合うサービスや商品を選ぶという点でもマネリテはマストです。例えば金融機関が推す投資商品は、あなたにとって必ずしもよい商品とは限りません。『プロが推してるんだから間違いないだろう』ではなく、ある程度の知識があれば『私にはリスクが高そうだからやめとこう』など自分で判断できます。
家計管理や投資も最初は誰かのマネでいいけど、慣れてきたら“自分で考えて選ぶ”ことがとても大切。それができれば活きたお金の使い方ができますよ」
お金についておしゃべりしよう
【サ】「マネリテ」と聞いて「うっ、難しそう」と尻込みする人もいそうです。
「日本人はお金のことをあまり話さない風潮があります。それでわからない、難しいと苦手意識を持つ方が多いのかも。うちの編集部なんて、みんなお金の話ばかりしてますよ(笑)。ポイ活やふるさと納税はもちろん、どの住宅ローンを利用してるとか、どこの株を買ったとか、すごくオープン。
そんなおしゃべりがきっかけで『私もやってみようかな』とか『こうするといいんだな』と思えたりして、マネリテがじわじわ上がっていきます」
【サ】なるほど。まずは身近な人とお金についておしゃべりしてみる、ですね!
マネリテは生活スキル
【サ】家計管理や節約もマネリテと言えますか?
「もちろん!それらも限られたお金をどう使うか、自分で考えて実践するものですからね。だから『難しそう』と身構えなくていい。そこから節税や投資など少しずつ知識を広げていけます。料理や掃除などの家事と同じように、今やマネリテも生きていくために欠かせないスキル。
マネリテがあれば、今あるお金をフルに有効活用して自分のやりたいことにトライできたり、家族と旅行など楽しいことにお金を使えたり、人生を目一杯楽しめます。まずは『マネリテを上げよう!』と意識することから始めてください」
【サ】マネリテがグッと身近になりました。ありがとうございました!
<教えてくれた人>
『ダイヤモンド・ザイ』編集長 熊谷久美子さん
創刊時より『ダイヤモンドZAi』に携わり、2024年より編集長に就任。『月刊マネー誌ザイが作った新NISA入門』など書籍も担当。公益社団法人日本証券アナリスト協会認定アナリスト。
※2023円8月~2024年7月/紀伊国屋書店、くまざわ書店、丸善ジュンク堂書店、未来屋書店/月刊誌、投資運用ジャンルなど
参照:『サンキュ!』2025年5・6月合併号「マネリテ上げて、お金に振り回されない人生を始めよう!」より。掲載している情報は2025年3月現在のものです。撮影/小田垣吉則 取材・文/神坐陽子 編集/サンキュ!編集部