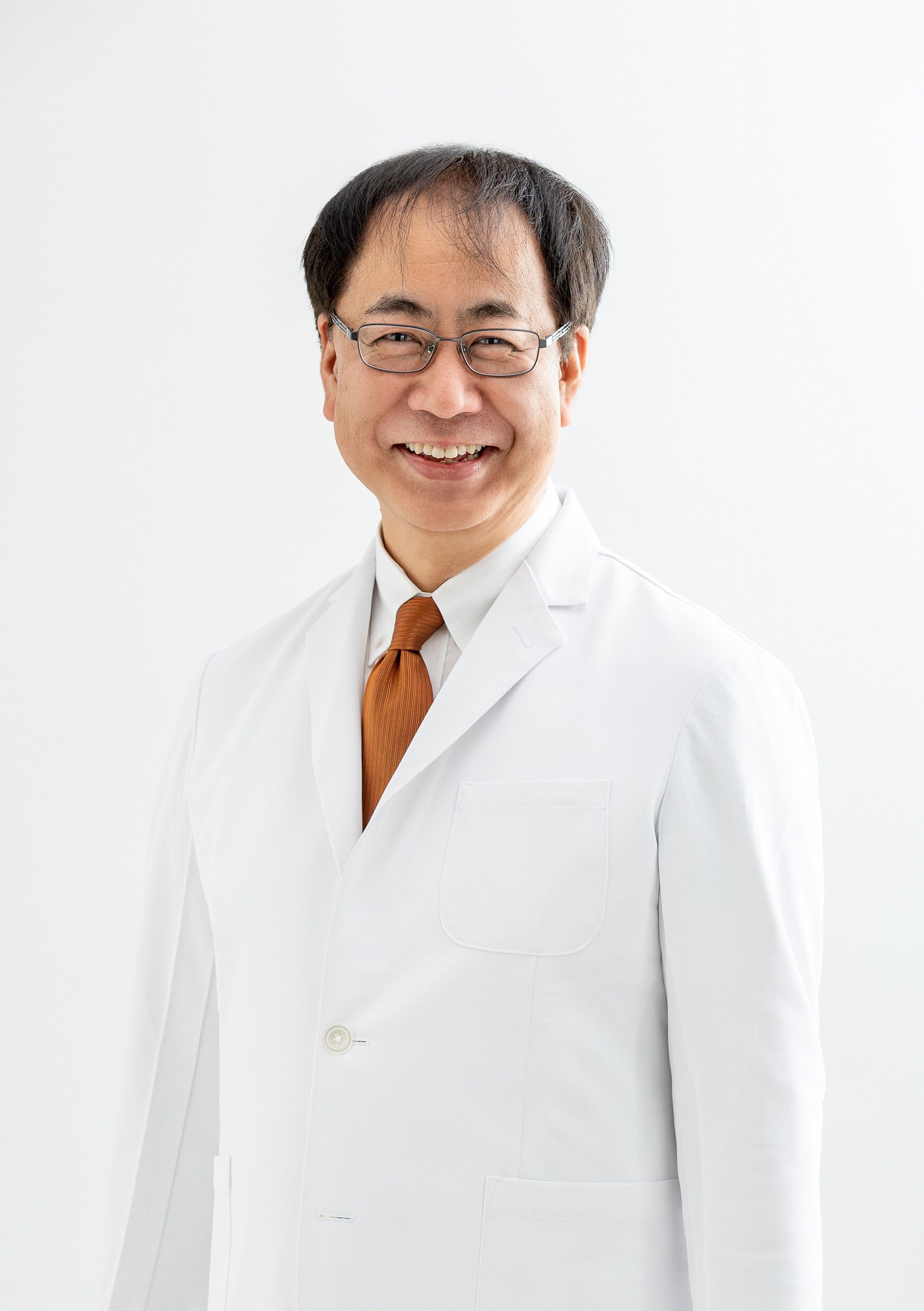「血液のがん」とも呼ばれる白血病。若い人に多いと思われがちですが、実はそうではありません。
白血病の詳しいお話を、血液やがん薬物療法などの専門医・指導医で、ひだまり内科クリニックの院長である伊藤公人氏に聞きました。
Q.白血病とはどのような病気ですか
血液中には、白血球、赤血球、血小板の3つの血球細胞が存在します。そのうち、白血球系の細胞ががん化して白血病細胞(病的な白血球系細胞)となり、増殖することで起こるのが白血病です。白血病は「血液のがん」とも呼ばれます。
白血病では、血液中の白血球数が増加するケースが多いです。しかし中には、白血病細胞が骨髄では増えていても血液には移行せず、血液中の白血球の数はとても少ない場合もあります。
白血病は、白血病細胞が急激に増える急性白血病と、比較的にゆっくりと増える慢性白血病に大きく分けられます。さらに増えている細胞の種類により、骨髄性白血病とリンパ性白血病に分けられます。それぞれの白血病で病状や治療、今後の見通しは異なります。
Q.白血病の原因や、なりやすい人の特徴にはどのようなものがありますか
白血病の原因については、まだ充分にはわかっていません。
発症されたかたの大部分において原因は不明ですが、以下の場合、白血病になるリスクが高くなるとわかっています。
・放射線の大量の被ばく
・化学療法や放射線療法を受けた
・ダウン症候群などの特定の遺伝性疾患がある
・特定のウィルス感染症(HTLV-1など)に罹患している
また喫煙者は、急性骨髄性白血病となるリスクが、非喫煙者に比べて1.6倍から2倍高まります。
慢性リンパ性白血病は、人種で発症のリスクが異なります。欧米人に多く、アジア人では稀な疾患で、人種による罹りやすさの違いがあると言えるでしょう。
「若者の疾患」と思われがちな白血病ですが、実際には高齢になるほど発症リスクは高くなります。
Q.白血病の自覚症状にはどのようなものがありますか
白血病では、血中の正常な血液細胞が減少することにより、さまざまな症状が出現します。
急性白血病の初期には、発熱、全身倦怠感、頭痛、関節痛など、風邪に似た症状が見られます。その後、貧血症状(動悸、息切れ、全身倦怠感など)、感染症状(高熱など)、出血症状(鼻出血、歯肉出血、紫斑など)が現れます。
白血病細胞がさまざまな臓器に浸潤(しんじゅん:広がること)すると、肝臓・脾臓やリンパ節の腫脹、頭痛、吐き気などの症状が起こります。
一方、慢性白血病は、疾患の進行が緩徐で初期症状に乏しいです。そのため、健康診断などで白血球数の増加を指摘されて、見つかることが少なくありません。
Q.白血病を予防することはできますか
白血病の予防はむずかしいです。ただし、禁煙・栄養バランスの取れた食事・適度な運動により、発症リスクをできる限り減らすことが、一定の予防につながるでしょう。
特殊なケースですが、成人T細胞性白血病では、HTLV-1というウィルスへの感染が発症の原因となります。そのため人から人へのHTLV-1の感染を防止することで、予防的に白血病の発症リスクを低減化できます。
Q.白血病を早期発見することはできますか
発見に関して、症状の進展が早い急性白血病を早期に見つけることは困難です。一方、進行が緩やかな慢性白血病は、比較的早期の段階で発見できる可能性があります。
慢性骨髄性白血病では、数年の慢性期を経た後、移行期、急性転化期へと移行します。慢性期は自覚症状に乏しいですが、この時期に適切な治療を開始できれば、寿命にほぼ影響がない状態に病状をコントロールすることができます。しかし移行期や急性転化期となると、病状コントロールはむずかしくなります。
いずれにせよ、定期的に健康診断を受診し、血液検査を行って、早期発見・診断することが極めて重要となります。
Q.白血病は治療できますか
白血病は治療できます。現在では医学の進歩により、治癒が期待できるがんのひとつとなりました。
白血病に対する治療法は、白血病の種類や患者さんの体の状態、年齢などによって異なります。
急性白血病は発症が急激なので、可能な限り迅速に治療を開始する必要があります。治療の主体は抗がん剤による薬物療法です。他のがんと比較すると、急性白血病は薬物療法の効果が高いです。基本的には複数の薬物を組み合わせて、体内にある白血病細胞を減少させる治療を行います。
急性白血病は、寛解導入療法、地固め療法、維持療法の3段階で治療を進めます。病状によってはさらに治癒の確率を高めるため、造血幹細胞移植を行うケースがあります。
慢性骨髄性白血病に対しては、特定の遺伝子異常を標的とした、チロシンキナーゼ阻害薬という分子標的治療薬を用いることで、良好な病状コントロールが期待できます。
かつては難治性であった白血病も、治療の進歩により寛解や治癒が期待できるケースが増えてきています。一方で、治療にはさまざまな副作用を伴うことが多く、治療効果の限界についても知っておく必要があります。
取材/文:山名美穂(Instagram「@mihoyamana」)
編集:サンキュ!編集部