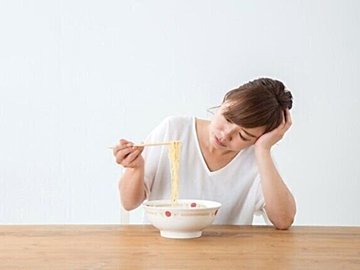いんげんは低カロリーでさまざまな栄養素を含む食材です。どのような栄養素が入っているのか、ダイエット効果は期待できるのかについてご紹介します。簡単に調理できるレシピも紹介していますので、いんげんを食事に取り入れていきましょう。

いんげんの種類
いんげんは、いんげん豆をさやのまま、成長しきる前に収穫して食べる「さや豆」の代表です。いんげんには丸くて細い種類と、平たく幅広な種類があります。また、最近では筋のない品種も増えています。旬は6~9月です。
いんげんは、ビタミンやミネラルなどの栄養素を含む緑黄色野菜の1種です。
いんげんのカロリーと栄養素
生のいんげん(さやつき)100gあたりのカロリーは23kcalです。ゆでたいんげん(さやつき)100gあたりのカロリーは、26kcalです。
いんげんに含まれるさまざまな栄養素について、具体的に見ていきましょう。
いんげんの栄養素
・食物繊維
・ビタミンB群
・ビタミンK
・タンパク質
・カリウム
いんげんの栄養素1:食物繊維
いんげんには食物繊維が含まれています。食物繊維は腸内の善玉菌を増やし、有害物質を吸着して排出することで、腸内環境を整えてくれる栄養素です。
食物繊維には水溶性と不溶性の2種類があります。これらはそれぞれ効果が異なっていて、バランスよく摂取することで、効果的に働くとされています。いんげんは、その2種類の食物繊維を両方含んでいます。
生のいんげん100gに含まれる食物繊維は、2.4gです。
いんげんの栄養素2:ビタミンB群
ビタミンB群とは、8種類の水溶性ビタミンの総称です。そのなかのビタミンB1は、糖質からエネルギーを産生するために必要な栄養素です。不足すると疲労の原因になる場合があります。
また、ビタミンB2は糖質、脂質、たんぱく質からエネルギーを産生するために必要で、不足すると成長障害、皮膚や粘膜の炎症を引き起こす可能性があります。とくにエネルギーを消費する活動が多い人は、不足しないように注意しましょう。ビタミンB6は、たんぱく質からエネルギーを産生したり、神経伝達物質の生成などに関与しています。
生のいんげん100gあたり、ビタミンB1が0.06mg、ビタミンB2が0.11mg、ビタミンB6が0.07mg含まれます。
いんげんの栄養素3:ビタミンK
ビタミンKは出血を止めることや、丈夫な骨づくりに作用する栄養素です。
ビタミンKの主な働きは、出血時に血液を固めて止血する成分を活性化することです。そのため、ビタミンKが不足しているときに出血すると、出血時間が長くなってしまう可能性があります。
また、骨の形成を促進する効果もあり、骨を丈夫に保つためにも必要な栄養素です。生のいんげん100gあたり60μgのビタミンKが含まれます。
いんげんの栄養素4:タンパク質
タンパク質は筋肉や臓器など、体を構成する成分として重要な栄養素です。
タンパク質は三大栄養素の1つで、エネルギー源としても使われます。タンパク質はアミノ酸の配列によって構成され、それぞれ異なる役割を担っています。タンパク質には、筋肉や臓器、肌や髪の材料となるだけでなく、正常な体を維持するために必要なホルモンや免疫物質なども構成し、体中へ栄養を運ぶ働きもあります。
生のいんげん100gあたり1.8gのタンパク質が含まれます。
いんげんの栄養素5:カリウム
カリウムは、細胞の状態や血圧を調節しながら、常に一定したよい体の状態を維持する役割のある栄養素です。
カリウムには高血圧を防ぐ役割があり、むくみも解消するともいわれています。カリウムの摂取量を増やすことによって、高血圧や脳卒中の予防、骨密度の増加につながります。
生のいんげん100gあたり、260mgのカリウムが含まれます。
いんげんはダイエットに効果がある?
いんげんには、腸内環境を整える食物繊維が含まれているため、ダイエットに効果的といえるでしょう。いんげんは低カロリーで噛み応えがあるため、食事をした満足感を得やすいです。
また、代謝に必要なビタミンB群も含まれているので、体を動かして消費エネルギーを増やすときに役立つ食材と言えます。
いんげんを使ったおすすめのレシピ
いんげんは筋があり、調理が面倒と思っている人も多いのではないでしょうか。しかし、筋のない品種のいんげんも増えてきています。
また、いんげんは下ごしらえをすれば冷凍保存が可能な野菜です。ここからはいんげんを使った3つのレシピをご紹介します。
いんげんのおすすめレシピ1:いんげんのごま和え
工程が少なく、料理初心者でもつくりやすいでしょう。とくにむずかしい作業がなく、特別な道具も必要ありません。調理にかかる時間も10分ほどと手軽。
緑が鮮やかないんげんのごま和えはお弁当のちょっとした隙間や、副菜として食卓に並べると、彩りを添えてくれる1品です。
いんげんのおすすめレシピ2:ささっとおかず。いんげんとベーコンのバター炒め
短時間でささっとつくれて、冷凍保存も可能なレシピです。冷凍で5日間保存が可能です。
ベーコンの塩気をいかして、バターとこしょうの風味を添えるだけで手軽につくれます。いんげんの緑とベーコンのピンクが鮮やかで、お弁当に彩りを加えてくれるでしょう。
いんげんのおすすめレシピ3:インゲンの肉巻き
冷凍いんげんを使用した、手軽につくれて食べ応えのある一品です。最近では冷凍いんげんも増えています。冷凍いんげんは事前に塩ゆでを必要としますが、塩ゆでする時間を含めても、調理時間は短いでしょう。
おかずがもう1品欲しいときにもおすすめの料理です。
いんげんをおいしく食べよう!
低カロリーでさまざまな栄養素が含まれるいんげんは、6~9月が旬の野菜です。
新鮮ないんげんを見分けるには、太さ・豆の形・ハリに注目してください。太さが均一で豆の形がはっきりしていないものや、ハリがあり、さやの先までピンとしているものは新鮮ないんげんです。
旬の時期に限らず、冷凍のいんげんも活用し、食事に取り入れてみてはいかがでしょうか。
監修者ミニコラム:いんげんは「豆だけ」と「さやごと」のどちらに栄養が多い?
いんげんは、未熟なうちに収穫してさやごと食べる「さやいんげん」、そのまま成熟させた豆を「いんげん豆」という区分けではなく、別々の品種です。そのため、育てている途中でどちらも収穫して食用するわけにはいかないのです。
<同量を“ゆで”で比較した場合>
・「さやいんげん」の方が多い主な栄養素:β-カロテン/ビタミンK/葉酸
・「いんげん豆」の方が多い主な栄養素:タンパク質/脂質/炭水化物/ほぼ全てのミネラル類
(栄養成分表では、「さやいんげん」=野菜、「いんげん豆」=豆類に分類されています)
エネルギー源として選ぶのであれば、「いんげん豆」。ビタミン補給として選ぶのであれば、「さやいんげん」が向いていると言えそうですね。