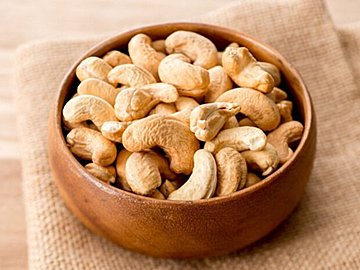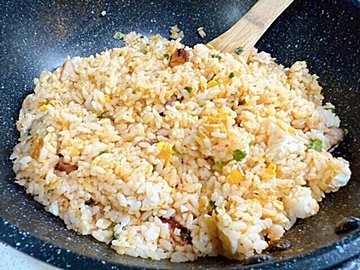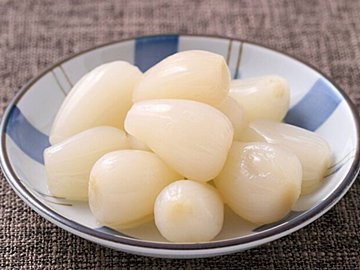キムチに含まれる栄養素には、健康によい作用を持つものが多い反面、とり方を間違えてしまうと体調をくずす危険性もあるのだとか!
管理栄養士と食生活アドバイザーの資格を持つライターのゆかりさんに、キムチの食べ方によって体にどのような悪影響が及ぶのかと、1日に食べてもいい量の目安について紹介してもらいます。

免疫力アップや腸内環境改善に!キムチを食べる「メリット」
キムチとは、白菜などの塩漬けした野菜などに、塩、唐辛子、にんにく、塩辛などを一緒に漬け込んで発酵させた韓国の家庭料理の一種です。食材、つくり方、地域などによって200以上の種類があると言われています。
塩気、辛味、うま味、甘味などが感じられ、本場韓国では白菜の収穫期に家族や親せきが集まり、大量のキムチを漬け込むのが冬の風物詩となっているんだとか。
そのままおかずとして食べるのはもちろん、ピビンパ(ビビンバ)や冷麺などの韓国料理にトッピングとして使われたり、チヂミに混ぜて焼くなどのさまざまなシーンで使われています。
そんなキムチには、おもに次のような栄養素が比較的多く含まれています(※)。
・ビタミンK
・ビタミンC
・ビタミンB6
・食物繊維
これらには、骨を丈夫に保つ、ストレスや風邪などの抵抗力を高める、正常な免疫機能を保つ、便通を促す、腸内環境を整える、などといった働きが期待できますよ。
そのほかに、発酵食品のため乳酸菌が豊富に含まれているという特徴もあります。
乳酸菌は、腸の中まで運ばれると大腸菌などの悪玉菌の繁殖を抑えて、腸内菌のバランスをとる作用が知られています。腸内で善玉菌が増えることで、ウイルスや病原菌に対する免疫力を高めることも期待できますよ。
このように、キムチを上手にとり入れることで健康増進だけでなく美容にもよい影響が期待できるでしょう。
※……日本食品標準成分表(八訂)増補2023年版に収録の「白菜キムチ」のデータを引用。
痔になったり太る原因にも?キムチを食べすぎる「デメリット」
多くのメリットが得られるキムチですが、過剰に摂取したり体質によっては思わぬデメリットが生じることもあります……。
消化管(喉~肛門)への負担が大きくなる
キムチには、唐辛子を多く使ってつくられる種類もあります。日本でよく知られている白菜のキムチは、真っ赤な見た目のものが一般的。その赤色の正体が、大量に含まれる唐辛子なのです。
唐辛子に含まれているカプサイシンという成分は、血中に取り込まれると副腎からアドレナリンを分泌させ、脂肪代謝などのエネルギー代謝や発汗を促進する働きを持っています。
ところが、とり過ぎてしまうと喉や胃腸などの粘膜を傷つけ、喉の違和感・声がれ・胸やけ・消化不良・下痢などを引き起こしてしまうことに……また、排便時に痛みを伴ったり、肛門の粘膜が傷つけられることで痔になることもあります。
なお、キムチに使われる唐辛子は、日本の唐辛子(鷹の爪など)に比べて辛さが1/2~1/3と言われていますが、それでも大量にキムチを摂取してしまうとカプサイシンのとり過ぎに繋がってしまいます。
胃腸の調子が悪いときに避けるのはもちろん、辛さが平気な人でも食べ過ぎには気を付けましょう。
目や鼻などに悪影響が出る
カプサイシンを大量にとると直接触れる消化管だけではなく、それ以外の粘膜にも影響を及ぼします。
その理由として考えられるのが、辛さの刺激による防御反応として副交感神経を活発化させると言われています。すると、体の中から異物を出す働きが強まり、涙や鼻水止まらなくなることがあるのです。
また、子どもや辛さに敏感な人は、吐き気、嘔吐、高血圧などの症状が現れることも……。
カプサイシンのメリットを期待してとり過ぎてしまうと、デメリットの方が多くなってしまいますので注意しましょう。
口臭や体臭が強くなる
キムチの種類によっては、ニラやにんにくなどが多く使われていることがあります。
これらの食材は、加熱せずに生のまま漬け込まれるため、刻んだりすりおろした時に発生するニオイの成分が残っています。
ニオイの成分は食べた直後に口からにおうだけでなく、成分が代謝されるまで16時間ほどかかり、その間に血液を通して全身を巡ると言われています。
そのため、大量にキムチを食べることで、ニオイの成分が血液を通じて、皮膚や呼気からニオイを発してしまうことも。
口臭や体臭が気になる人は、とくに食べ過ぎないようにしましょう。
むくんだり肥満になる
白菜のキムチには、一般的な白菜の漬物よりも食塩が多く含まれています。そのため、キムチの食べすぎによって、塩分のとり過ぎが起こってしまいます。
体内で塩分が多くなると、その濃度を薄めて一定に保とうとし、体内に水分が多く溜め込まれてしまいます。すると、むくみが起こってしまうのです。
また、塩分の多い食事は食欲を増進する作用もあわせ持ちます。食事量が増えることでエネルギーのとり過ぎとなり、消費しきれない分は脂肪として溜め込まれ、体重増加に繋がってしまうことに……。
ダイエットにも役立ちそうなキムチですが、食べるのは適量に留める必要があると言えるでしょう。
キムチを楽しむ量とタイミングは?
上記のとおり、キムチに含まれる栄養素にはメリットとデメリットの両方があります。
そこでここからは、安心してキムチを楽しめる量とタイミングについて解説していきます。
健康な成人は1日にどれくらい食べても大丈夫?
キムチだけで、カプサイシンの1回の推定許容量を超えることは不可能です(鷹の爪1gで1mg、体重kgあたり5mgとされています)。
しかし、体調が優れない場合や辛さに敏感な人にとっては、それ以下の量であっても悪影響が現れることがあるため注意を要します。
ちなみに、食塩量で計算した場合、つぎのような目安量を求めることができます。
日本人の食事摂取基準(2020年版)によると1日の食塩摂取目安量は、健康な成人男性で7.5g未満、健康な成人女性で6.5g未満とされています。そのことから、1食あたりの塩分摂取量は男性で2.5g、女性で2.2gまでに抑えるのが理想的です。
100gあたり食塩相当量が2.9g白菜のキムチで換算すると、男性は85g、女性は75g食べることでその食塩量を満たしてしまうことに。キムチ以外にも食事に食塩が含まれることを考慮すると、その半分以下に押さえておくのが妥当ではないでしょうか(参考:味噌汁1杯で食塩1gが前後含まれます)。
ただし、3食で100g以上食べてしまうと、キムチの種類によってはにんにくのとり過ぎに繋がる可能性があります。ニオイを気にするのであれば、先述したような目安量を3食毎回食べる、ということは避けた方がよいと言えるでしょう(生のにんにくは5gまでが安心して食べられる目安です)。
どのタイミングで食べるのがいい?
キムチに含まれる乳酸菌を生きたまま腸に届けるために、就寝中に胃酸の分泌が抑えられる夕食にとるのが望ましい、と言われることもあります。
ですが、乳酸菌は死んでいても免疫力の活性化や腸内環境の改善などの作用を発揮するため、基本的にはいつ食べてもよいと筆者は考えています。
なお、食事の最初ではなく、ほかの料理を口にしてからキムチを食べることがおすすめ。この理由は、カプサイシンの粘膜への刺激を少しでも抑えるためです。
タイミングとは別に、キムチを選ぶ際に大切にしてほしいポイントは、「発酵キムチ」の認証マークが付いているかを確認すること。
というのも、市販のキムチの中には、調味液に浸けただけで発酵させていない浅漬けタイプも扱われているからなのです。
「発酵キムチ」の認証マークは韓国産のものに限定されますが、国産のキムチであっても「熟成発酵」や「乳酸発酵」などの表記があれば乳酸菌を含んでいると考えられます。
せっかく食べるのであれば、このように効果が期待できるキムチを選ぶことをおすすめします。
正しい量を把握できていれば、キムチはメリットが多い食品です。キムチのメリット・デメッリトを理解し、上手にとり入れていきましょう。