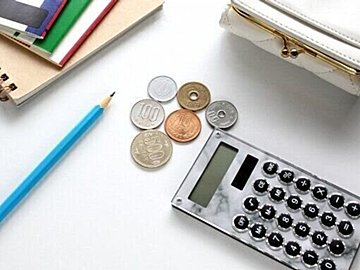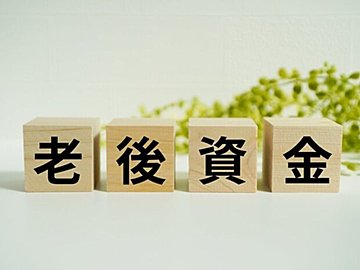2024年1月から始まる「新NISA(ニーサ)」。節約アドバイザーの丸山晴美さんは「投資をするならお得な制度なので、ぜひ活用してほしい」と言います。そのためにやっておきたい家計の振り返りと、私たちが知っておきたい新NISAのメリットなどについて聞きました。
なお、今回ご紹介する情報はすべて2023年10月時点の取材情報を基にしています。

監修: 節約アドバイザー 丸山晴美
22歳の時に節約に目覚め、1年で200万円を貯めた経験がメディアに取り上げられ、その後コンビニ店長などを経て...
みなさまこんにちは。節約アドバイザーの丸山晴美です。
お金にはトレンドがあって、その情報をキャッチできるか否かで、得する人と損する人に分かれます。私はみなさまに“お金の旬の情報”を“わかりやすく”お届けしていきたいと思います。今回のテーマは「新NISAについて」!
来年からの貯蓄に向けて「振り返り」と「仕組みづくり」を
今年ももうすぐ終わります。2023年はどのくらい貯蓄ができましたか?
12月は年賀状の用意や大掃除など、年末年始の準備で忙しくなるので、11月中に「2023年のお金の振り返り」をしておきましょう。
「2023年のお金の振り返り」とは、2023年の初めに立てた家計の計画や貯蓄額が、目標通りにできたかできなかったかをチェックし、その原因を見つけ、対策を立てること。これをすることで、貯め力ややりくり力が確実にアップします。
毎月貯められる金額も具体的に見えてくるので、その金額を「先取り貯蓄」する「仕組み」を作ることも重要なポイント。先取り貯蓄とは、給与など収入が入ったタイミングであらかじめ決めた金額を先に貯蓄にまわすことで、この仕組みをつくっておけば自然とお金が貯まります。
先取り貯蓄の方法には、銀行の定期積立だけでなく、積立投資も検討することをおすすめします。
特に2024年1月から新NISA(ニーサ)がスタートします。投資をするならお得な制度ですし、投資は長期的な視野でコツコツとすることが大切なので、早く始めるほど効果的と言えます。
新NISAは非課税保有期間が「無期限」になって断然お得!
新NISAとはどういうもので、これまでのNISA制度とどこが変わるのか、知っておきましょう。
NISAとは、2014年に金融庁が導入した日本版の少額投資非課税制度で、売却益などにかかる税率(20.315%)が非課税になるのが特徴です。
現行のNISAには以下の2種類があります。
■一般NISA:年間投資上限額120万円、非課税保有期間5年間
■つみたてNISA:年間上限額40万円、非課税保有期間20年間
これが2024年1月からの新NISAでは、一般NISAは「成長投資枠」、つみたてNISAは「つみたて投資枠」という名称に替わり、年間投資上限額や非課税保有期間が以下のように増えます。
■一般NISA:年間投資上限額120万円、非課税保有期間5年間
↓
■成長投資枠:年間投資上限額240万円、非課税保有期間は無期限
■つみたてNISA:年間上限額40万円、非課税保有期間20年間
↓
■つみたて投資枠:年間投資上限額120万円、非課税保有期間は無期限
さらに、現行のNISAでは、「一般NISA」と「つみたてNISA」のどちらか1つの口座しか開設できませんでしたが、新NISAでは「成長投資枠」と「つみたて投資枠」として、1つの口座で併用することができるようになります。
これにより、個人あたりの年間非課税投資枠が最大360万円になり、総枠としての非課税保有限度額は1800万円。そのうち、成長投資枠の上限が1200万円になるため、600万円はつみたて投資枠で投資をすることで満額になります。
つまり、新NISAは現行のNISAに比べ「より多くの資金を」「より長い期間」「より自由度が高い環境」で資産運用ができるということ。個人が投資をする際に重要とも言える「長期」「分散」「積立」が、よりやりやすくなったと言えるのです。
すでにNISA口座を持っている場合、開設している金融機関に自動的に新NISA口座が開設されるため、手続きの必要はありません。
まだNISA口座を作っていない人は、年内に現行のNISA口座を作ることで、スムーズに新NISAがスタートできます。毎月1万円でもいいので、まずはできる金額から始めてみてはいかがでしょうか?
証券会社によっては、貯めたポイントや100円から投資信託が購入できるNISA口座もあります。
貯蓄は家計の状況や目的に合わせ臨機応変にすることも大切
新NISAのメリットをご紹介しましたが、貯蓄には優先順位がありますから、なんでもかんでも新NISAの口座で投資をすればいいということではありません。
投資は長期的な視野でお金を運用するものなので、マイナスになるリスクも当然あります。つまり、1~2年など短期で使う予定があるお金を貯める場合は、銀行の定期預金なので確実に貯めた方がいいでしょう。
私の場合、1年前に息子が歯列矯正を始めることになり、その費用80万円を捻出する必要がありました。本人の強い希望で急に始めることになったため、そのための貯蓄もしていませんでした。そこで、家計の振り返りをして、息子の習い事や通信費などを細かく見直し、手数料などがかからない分割コースを選んで、最初に20万円、都度に5万円を分割払いするようにしました。
その支払いが先月ようやく完了!息子の歯並びもきれいになり、これもある意味「投資」としてよい出費だったと私は考えています。でも、せっかくやりくりできる状況を作ったので、今後は2万円だけ家計に戻し、残りの3万円は毎月積み立てている投資の金額にプラスしていく予定です。
過去に戻って貯め直すことは絶対にできません。ですから、いちばん若い今、できることは何かをしっかりチェックして、できるだけ早く「お金が貯まる仕組み」を作っておくことが大切です。
※投資には元本保証はありません。損失のリスクも検討し、自己責任のうえで行ってください。
取材・文/かきの木のりみ